2023年6月30日に公開の映画「小説家の映画」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「小説家の映画」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
小説家の映画が視聴できる動画配信サービス
現在「小説家の映画」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「小説家の映画」が配信中です。
小説家の映画のあらすじ
長年創作から遠ざかっていた著名作家のジュニは、音信不通となっていた後輩を訪ねる旅の途中、ソウルを離れた静かな場所で偶然の出会いを果たす。出会った相手は、第一線を退いた人気女優のギルスだった。初対面にも関わらずギルスに惹かれたジュニは、彼女を主演に据えた短編映画を自ら撮りたいという、予想外の提案を投げかける。かつて名声を手にしつつも内に葛藤を抱えたふたりが織りなす、思いがけないコラボレーションの行方はいかに――
小説家の映画の詳細情報
「小説家の映画」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
小説家の映画の公式PVや予告編動画
「小説家の映画」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
小説家の映画を見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
小説家の映画を無料で見る方法は?
「小説家の映画」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
小説家の映画のよくある質問
-
Q映画『小説家の映画』の基本的なあらすじは何ですか?
-
A
『小説家の映画』は、創作することへの葛藤とそれに向き合う人々の姿を描いた作品です。主人公の小説家は、新しい映画企画のアイデアを探しながら、様々な人物と出会い、彼らとの交流を通じて自身の創作意欲を再発見します。
-
Q映画『小説家の映画』に登場する主要なキャラクターは誰ですか?
-
A
『小説家の映画』では、主人公の小説家を中心に、彼が出会う映画監督や若手女優などが主要なキャラクターとして登場します。それぞれの人物が持つ個性的な背景や悩みが物語を深めていきます。
-
Q映画『小説家の映画』のテーマは何ですか?
-
A
映画『小説家の映画』のテーマは、創作の苦悩とその先にある自己発見です。登場人物たちは、自分の表現方法を模索し、創作の意義を見出そうと奮闘します。
-
Q『小説家の映画』の制作スタッフについて教えてください。
-
A
『小説家の映画』の監督は、作品の中で現実と幻想の境界を巧みに描くことを得意とする人物です。脚本も自ら手がけており、独自の感性と語り口が印象的です。
-
Q映画『小説家の映画』はどのような評価を受けていますか?
-
A
映画『小説家の映画』は、観客からはその繊細なストーリーテリングと深いテーマ性が高く評価されています。特に、登場人物の心情描写やリアリティのある演技が好評です。

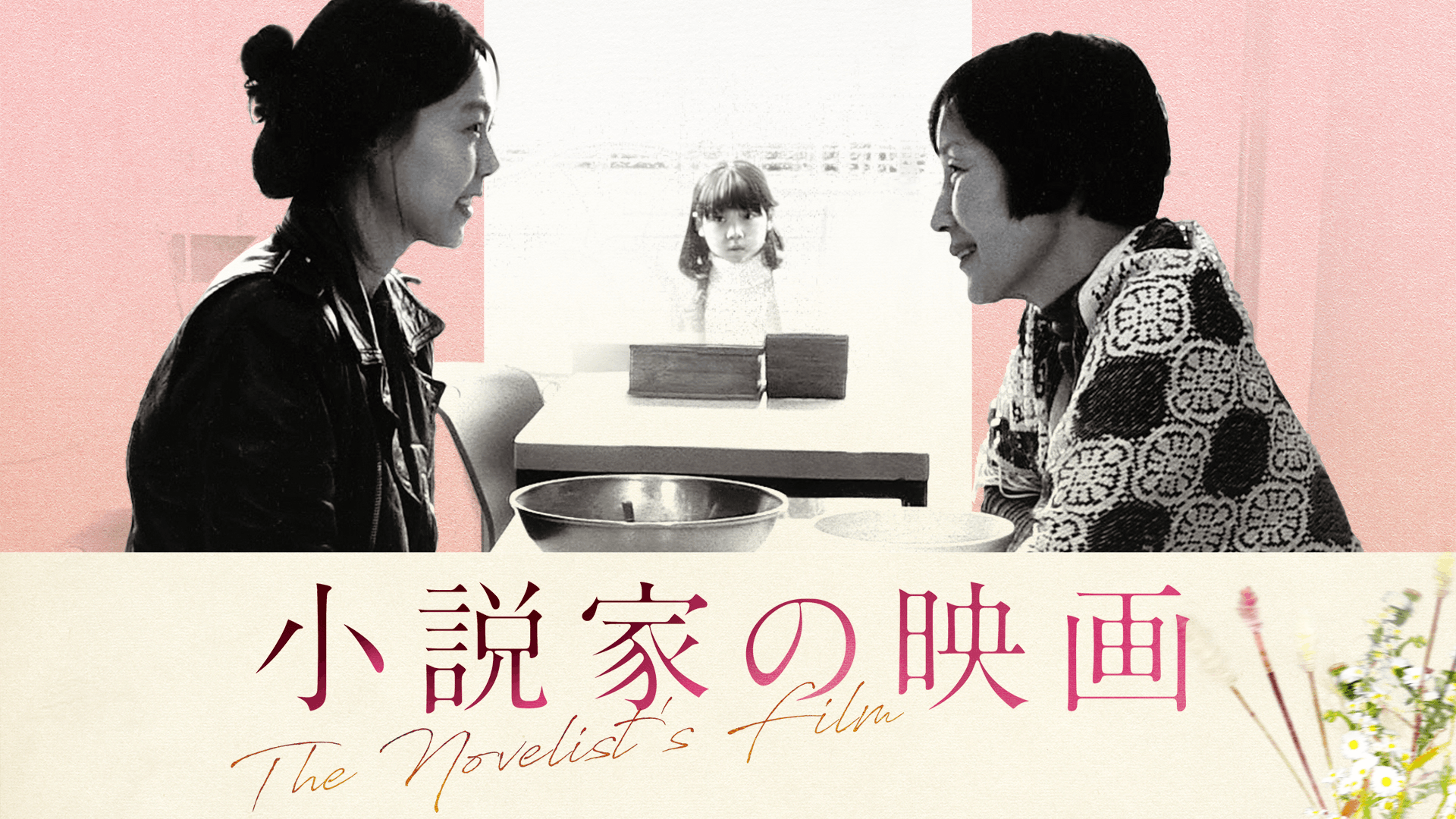



小説家の映画の感想・評価
一つ一つのカットが際立って長く、私なら早々に会話を打ち切ってしまいたくなるほどの気まずさを感じる場面が続き、共感性羞恥が襲ってきた。ホン・サンスの魅力は、本音と建前が同時に存在することにあり、私もその点を楽しみにしているのは確かだ(加えて、癇癪を起こす金切り声)。しかし、気まずい会話にはどうしても視線をそらしたくなる瞬間もある。それだけリアルに描かれているのだ。ジュニ氏は、カリスマというよりも特徴のある人物という印象だ。彼はこだわりが強く完璧主義なため、人付き合いが苦手である。触れられたくないことには言葉を濁すが、他人に対しては率直に物を言う。これは一筋縄ではいかないキャラクターだ。
特に大きな展開はなく、モノクロの画面で普通の会話が心地よいリズムで進んでいく。韓国のジャームッシュ作品のようにも感じられる。
ストーリーが強引に引っ張るわけではないため、ほとんどが敬語で会話が織りなされるのが魅力的だ。コロナ禍を反映したマスクなどが存在感を示し、登場人物たちの距離感の微妙なニュアンスが伝わってくる。敬語が通じる国同士であることは、本当に良かった。
25分頃、主人公は映画監督に対して怒っていないと言いながら、実際には不満を抱えている。彼はストレートにその不満をぶつける。
このシーンでは、皆が紙コップのコーヒーを飲んでいるが、コップをテーブルに置く時に空っぽの音がして、ダミーであることがわかる。
若い女優役のキム・ミニが登場する。
スランプ中の小説家である主人公は嫉妬に駆られ、さらにキツい発言を映画監督にぶつけ、監督の奥さんが激怒。後ろを向いたまま監督を引っ張って即帰宅する姿が面白い。
映画なんて撮れないくせに、「撮っちゃおうかな」と言う主人公は厳しい。女優の甥が映画の勉強中だと聞くと、利用しようとするが、絶対に良い映画ができないことは明らかだ。
最初に訪れた後輩の店に戻り酒を飲む主人公。若い女優の夫が有名なため、絶対に出演してほしいと願い、そうしないと脚本が書けないと嘘をつく。さらに「ストーリーなんて大事じゃない」と自分の基準を下げる。
結局、女優の夫は出演してくれなかったが、甥がカメラマンとして参加し撮影を行う。その上映後、キツい仕上がりを見て、女優は力が抜けて呆然としている。
スランプを乗り越えるためには新しいことに挑戦する気持ちが重要だが、主人公のようにありのままを受け入れていない邪念を抱えていては、何もうまくいかない。
この精神状態には共感できる部分が多く、むしろ理解しすぎるからこそ辛い。
この会話の中で、ドキッとする瞬間や気まずさを感じる場面が、なんとなく好きだ。さらに哲学的に展開するところもあり、評論家が好みそうな映画だと思う。キム・ミニはスタイルが本当に抜群。ホン・サンスの作品を見るときはいつもお酒を飲みながら脈絡なくダラダラと観てしまうので、いまだに何も理解できていない気がする。
美しいものを見つけるために世界の果てまで行く必要はない。隣にそれは存在する。
私はホン・サンスがレイモンド・カーヴァーの真の後継者だと感じています。
不必要な要素をすべて排除し、日常の中に潜む微妙な感情を見事に映し出しています。
とはいえ、映画表現に必須な技術も確かに備えており、例えば声の演技の仕方に関しては特に印象的です。
もし声を日常のように自然に扱ってしまえば、セリフがかき消されてしまうこともあります。
セリフに強調が加わると日常感が薄れ、演者が舞台俳優のように感じられることもあり得ます。
その微妙なバランスを保ちながら、セリフと日常の会話の中間を巧みに表現するのが素晴らしいと思いました。
ミニマリズムを体現する監督の中で、彼は最も素晴らしい作品を私たちに届けているのではないでしょうか。
感想を書こうとすると、つい考えが広がってしまい、以下は駄文かもしれません。映画を観ていることを強く意識させられる作品でした。ジュニの「本物の感情の記録」という言葉には深く共感します。感情はカメラで完璧に映し出せないからこそ難しいのですが、ズームやカットだけに頼らない映像の中で、本心が読みづらい会話を耳にしても、心に響く感情が伝わる瞬間がある。それこそが映画の感動の源泉なのだと思います。ギルスが映画を観終え、屋上で日常へ戻っていくように、私たちも日常へと戻っていきます。最後のシーンは、ホンサンスのキムミニへの愛情があまりにも激しく、観る者を引くほど印象的でした。
外へ出て、出会う人とできるだけ率直に言葉を交わし、流れに身を任せよう。今、スランプのただなかにいる小説家である私がこの映画を観て、素直にそう感じました角田光代(作家)
角田光代(作家):「ただ人と人が会話をしているだけで、こんなにも面白いのは、スマホの保護フィルムに潜むあの気泡のような気まずさが、きちんと映っているからだろう。終電間際、駅の改札でケンカをしているカップルの、あの感じには目を離せない。」
尾崎世界観(ミュージシャン):「終電間際のあの場面の気配を、スマホの保護フィルムに潜む気泡のような気まずさがきっちり映し出す。会話だけでここまで引き込まれる映画はそうない。」
西川美和(映画監督):「ホン・サンスの映画を眺めると、いろいろと盛り込もうとしている自分の企みが、何なのか見失いそうになる。何事も起きない『ホン・サンス』の側にこそ、人生の真髄があり、よりスリリングだと感じる。『創り続ける』ことの嘘や怖さを、静かに詰められる感覚だ。」
筒井真理子(俳優):「小説家は透き通るような女優の笑顔を映画に切り取り、その笑顔の奥に映る、苦い人生を生きてきた自分が大切にしてきたもの。それはホン・サンスそのものだろう。もう一度あの笑顔に会いたい。」
岩井志麻子(小説家):「小説家の頭の中には映画館があり、そこにかかる映画は、色がなくても色彩豊かだ。現実が物足りないから映画を観るのではない。映画を観れば現実が豊かになるから、観たいし、作りたい。」
ヒコロヒー(お笑い芸人):「何を見せられているのか、何て凄いものを見ているのかという気持ちと、同時に湧き上がる感動がまったく同居していた。独創的な会話劇と個性的な表情で、彩り豊かな素晴らしい映画だった。」
酒井順子(エッセイスト):「自分の陣地を離れていくこと、会話を重ねることの可能性を示す作品。出会いと会話が、過去を越えた世界を淡々と切り開いていく。」
山内マリコ(小説家):「イ・ヘヨンの理知的な佇まいと、ある種の無邪気さが風を通して伝わってくる。心の浮き立ちに正直に、手話を教わってみたり、あなたで映画を撮りたいと語ってみたり。静かに人生を変えた一日を描く、中年女性の寓話のような物語だ。」
宇垣美里(フリーアナウンサー・女優):「生々しい愛に満ちた微笑みも、ラストに見せる感情を詰め込んだような形容し難い表情も、そのすべてが、キム・ミニの魅力に私を貫かれた理由だ。」
岩松了(劇作家・演出家・俳優):「『その先まで行ってキミは易々と間違いを犯すのか?』ホン・サンスの映画は、観るたびにそんな貴重な問いを私に投げかける。私にとって、そんな貴重な映画だ。」
長島有里枝(アーティスト、作家):「現代社会を新自由主義的に解釈しがちな営みと、私たちへの痛烈な批判と挑戦。対抗策として描かれるのは正直さ、純粋さ、そして姉妹のような友情。既存の価値基準では測れないこの芸術を、すぐには理解できないものとして長く愛したい。」
深田晃司(映画監督):「もともとシンプルだったホン・サンスの映画が、さらに研ぎ澈まされ、当たり前のように楽しむ映画たちが、いかに多くの作為で武装しているかを露わにする。私たちの生きる世界と同じ地平に静かに佇む映画それ以上でもそれ以下でもない美しさ。」
枝優花(映画監督・写真家):「めんどうな人々の、なんとも言えない絶妙な会話をひたすら追い続けた先に待つ、キム・ミニの表情。結局、監督の掌の上で92分間、転がされる。」
中田クルミ(俳優):「ワンシーン・ワンカットの長回し。まるでホームビデオを見ているかのような私的な時間。俳優たちの何気ない会話。そこに存在する自然な音と光と空気。そのすべてが愛おしい。」
IndieWire:「これまでにないほどパーソナルで、芸術の自由に捧げられた酔狂な叙情歌。」
The Film Stage:「表現そのものへの、ささやかな賛歌。」
The New York Times:「本作はチェーホフ流の研究であり、つまりそれは曖昧で、説明もなく、自発的で、整然とした動機や結果もないまさに人間の真の生き方そのものに関する研究である。」
#声_角田光代 #声_尾崎世界観 #声_西川美和 #声_筒井真理子 #声_岩井志麻子 #声_ヒコロヒー #声_酒井順子 #声_山内マリコ #声_宇垣美里 #声_岩松了 #声_長島有里枝 #声_深田晃司 #声_枝優花 #声_中田クルミ #声_IndieWire #声_TheFilmStage #声_TheNewYorkTimes
【第72回ベルリン映画祭 審査員グランプリ】
『それから』はホン・サンス監督の作品で、ベルリン映画祭コンペティションに出品され、審査員グランプリを獲得しました。
最近、ホン・サンスの作品に少しずつ惹かれています。彼はミニマリズムを駆使しながら、人間関係の微妙さを巧みに表現しています。
物語は、書けなくなった小説家のジュニが、偶然出会った女優と短編映画を制作しようとするところから始まります。女優役はお馴染みのキム・ミニが演じています。
とても楽しめました!女性が次々と人と関わる、そのシンプルなストーリーですが、ホン・サンス特有のユーモアとシニカルな人間描写が絶妙に表現されています。
タバコや酒を交えつつ、一見何気ない会話の中に深い人間哲学が垣間見えます。彼の作風は安定して面白いです。
短編映画の後、キム・ミニが見せる何とも言えない表情。会話劇はいつものスタイルですが、その裏にある複雑な人間の感情や関係を見事に描写しています。流石の一言です。
#第72回ベルリン国際映画祭
ホン・サンス・マラソン#8: キム・ミニが出演する映画は、男女間の軋轢と個人の内省を強く描く作品が多いという印象。
キムミニを観たくなった。
途中で、モノクロとカラーの境目が曖昧になって、思わず最初に戻った。最初の印象は何だったのだろう?小説家の神経質な部分には共感できる。みんなカリスマという言葉が好きだけれど、大好きな俳優から言われると素直に受け入れてしまい、もったいないと言う監督には反発しつつも、自分も似たようなことを言われたら戸惑ったり、人との話の間合いや気まずさ、不自然さの中に潜む自然さが描かれていた。最後のブーケは美しかったな。
ホン・サンスがみんなに好かれるのは理解できるけれど、具体的に何が魅力なのか不思議だ。しかし、私もその惹かれ方には納得できる。
心が震えるって、こういうことだったのか。ドラマティックな展開は一切なく、淡々と続く会話劇がすとんと進んでいく。具体的なことは何一つ語られないのに、登場人物の胸の震えは手に取るように伝わってくる。そこに宿る情熱、見えないものを映し出す力それがホン・サンス監督の作品の魅力として強く感じられた。初めての監督作だったが、その凄さはよく理解できた。退屈さを感じさせず、サクッと観られて、それでいて終盤には「え、これで終わり?」と意表を突かれる人もいるかもしれない。好みは分かれるだろうが、私はこの映像体験が好きだった。#ski鑑賞録2025年
ホン・サンス監督の作品は相変わらず印象的です。
イ・へヨンさんが演じる小説家の苛立ちと、キム・ミニさんが演じる女優の控えめな態度の対比が素晴らしかったです。
小説家の後輩である女性は常に不満を抱えている様子が気になりましたし、最後の映画は様々な思索を促すユニバースでした。
定点ショットから大胆なクローズアップへ移る不安定な視点。ふとした随意的注意に宿る揺らぎ。現状の反復と、新たなスタートの差異。
なぜここまでシンプルなのに面白いのか、逆に革新的に感じる。
考えてみると、映像がしっかりしていて、最小限のカメラワークでも動きがある。キャラクターや会話の面白さが一番の魅力だが、映像も引き込まれる要素だ。全体の構造が回りくどくて面白い。
一人で作業する作家とチームで協力する映画監督の違いを感じるよ。作家の内省的な自問自答が、作品や初監督作にも表れているようだ。
映画を観たギルスは驚いたのではないか?感動を引き起こすようなご都合主義ではないのも、まさにホン・サンスらしさだ。
監督が余韻に浸っている後ろ姿が面白い。