2018年1月27日に公開の映画「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅が視聴できる動画配信サービス
現在「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」が配信中です。
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅のあらすじ
フランス・パリで株式仲買人としてキャリアを始めたゴーギャンは、趣味として絵を描くようになった。しかし1882年、パリの株式市場が大暴落し、それまでの裕福な暮らしは一変する。絵を生業とする決意を固めるも、生活は窮乏に陥り、最愛の妻と子どもと離ればなれになる。その後、わずかな資金を手にタヒチを訪れた彼は、現地の風景と人々に強く魅了される。やがて美しいテフラという娘と結婚するが、資金の枯渇は続き、彼らの楽園にも貧困が忍び寄る。やがてテフラの感情も彼のもとを離れていくのだった。)
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅の詳細情報
「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 監督 | エドゥアルド・デルック |
|---|---|
| 脚本家 | エチエンヌ・コマール トマ・リルティ |
| 出演者 | Tuheï Adams マリック・ジディ ヴァンサン・カッセル |
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | ドラマ |
| 制作国 | フランス |
| 公開日 | 2018年1月27日 |
| 上映時間 | 102分 |
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅の公式PVや予告編動画
「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅を見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅を無料で見る方法は?
「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
ゴーギャン タヒチ、楽園への旅のよくある質問
-
Q映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』のあらすじは何ですか?
-
A
映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』は、フランスの画家ポール・ゴーギャンが現実逃避と創造的なインスピレーションを求めてタヒチに渡る物語です。そこで彼は土地の文化や人々と触れ合い、新たな芸術の道を切り開いていく様子が描かれています。彼の人生と芸術における試練と成長の過程が中心となります。
-
Q映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』の監督は誰ですか?
-
A
映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』の監督は、エドゥアルド・デルックです。彼はこの作品において、歴史的な画家であるポール・ゴーギャンの人生を丁寧に描き出しています。
-
Q『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』でのポール・ゴーギャンのキャラクターはどのように描かれていますか?
-
A
『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』では、ポール・ゴーギャンは芸術に対する情熱と理想を追い求める人物として描かれています。彼は自身の内面と向き合いながら、新たな暮らしと芸術作品を試み、また現地の人々との関係を築く姿が印象的です。
-
Q映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』の音楽について教えてください。
-
A
映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』の音楽は、クリストフ・ジュリアンが担当しました。映画の舞台であるタヒチの情景に合わせた音楽が、ゴーギャンの旅と内的成長を豊かに表現しています。
-
Q『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』と原作との違いは何ですか?
-
A
映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』は、ポール・ゴーギャンの実際の体験を基にしたフィクションですが、いくつかの芸術的解釈や脚色が加えられています。作品はゴーギャンの内面的探求に重点を置きつつ、ストーリー性を強調しています。





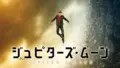

ゴーギャン タヒチ、楽園への旅の感想・評価
2026年の初映画は『ゴーギャン』です。
彼は株式仲買人として一時は成功を収めたが、株式市場の大暴落によって収入が大幅に減少し、画家としての道を選びました。
パリを後にし、タヒチを愛し、最終的にはタヒチで命を落としました。
ゴーギャンの作品は魅力的ですが、この映画は少し退屈かもしれません。
タヒチはもちろん、ハワイやマオリ系を含むポリネシア系の女性の描き方には偏りが感じられ、被写体としての魅力を過小評価している印象を受ける。フランス領へ行くならベトナムを選ぶべきだった、という意見には一定の理解がある。タヒチを舞台にした映画としてはヌード描写が物足りないと感じる。こんな作品を見るくらいならモームの『月と六ペンス』を読む方が良い、という見解にも頷ける。ちなみに原田マハはこのゴーギャン像にゴッホ殺しの嫌疑を掛けるという大胆な設定を用いながら、それでも全体としては退屈だと評される『リボルバー』という小説を執筆している。
絵画を題材にした映画の制作陣は、絵の描写に飽きてしまっている。芸術家を描く映画にありがちなスキャンダラスな要素を取り上げたシナリオ。
ストーリーを追うと、苦難が続く厳しい人生の様子が浮かび上がります(多くは自分自身の選択から来ています)。
創造への欲求や情熱が、パトロンや家族の支援なしに、また世間からの評価も得られないまま、執拗に表現され続ける様子はとても印象的でした。
ただ、信じるものが本当にあるかというと、迷いや妥協が随所に見受けられます。
精神的にも肉体的にも未熟さを抱える孤独な初老の貧乏画家という印象が強いです。
だからこそ、その抗おうとする姿勢には痛みが伴い、私自身も同じような悔しさや怒りを感じてしまいました。
うーん、もう少し深掘りしてほしかった。生活の描写は見えるけれど、絵についてはほとんど触れられていない。描いている姿だけが強調されている印象だ。
パリに嫌気がさしたゴーギャンは、妻と子どもたちを連れて楽園タヒチへの移住を考える。しかし、妻が彼の元を訪れると、その思いに愛想を尽かし、最終的にゴーギャンは一人でタヒチへ向かうことになった。
原始のイブテフラと出会い、貧しいながらも情熱的な日々を過ごしていたが、その幸せは長続きせず、すべてを失ったゴーギャンは疲れ切った姿で帰国することになった。彼の姿には同情の余地があるが、実際にはテフラはわずか13歳であり、この状況には美化しすぎの側面もある。
教会で響くエキゾチックな讃美歌は非常に美しかった。
理解できないことが山ほどあって、頭の中は疑問だらけでした。
タヒチ島について調査を行ったが、その魅力を感じることはできなかった。
普段、ヴァンサン・カッセルにはあまり惹かれないが、この映画に関しては、彼が出演していなければ最後まで観ることはなかっただろうと思う。
しかし、現代において何もないタヒチ島に行き、絵を描く意欲と実行力には感心させられる。貧困の中でも絵を描き続ける姿勢は素晴らしい。情熱があればこそ、技術も向上し、結果に結びつくと信じたい。
【オリエンタリズムに染まる】
ゴーギャンはゴッホと共同生活を送り、その後決別した。耳を自ら切り落とした事件は広く知られている。マルティニーク島やタヒチでのインスピレーションを得たとされ、身分差による軋轢が原因だと考えられてきたが、実際にはゴーギャン自身も貧困に苦しんでいた。
ゴーギャンは株式仲介人として実業家の成功を収めつつ、文明病を拒む姿勢から絵画へと転じた。ゴッホの死後に評価が高まったように、ゴーギャンも生前は貧困に喘いだという。
では、タヒチでの生活はどうだったのか。『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』を観れば彼の心理的側面が見えてくる。アンドリュー・グレアム=ディクソンの『世界の美術』によれば、裕福な生活から離れるように画家になったと読み取れる解釈がある一方で、パリの株式市場の恐慌がゴーギャンの人生を大きく変えたともされる。
株式だけでなく絵画の価値も下落する状況の中、仲間からタヒチへの逃避を勧められる。金銭や遠い地へ移ることへの不安を抱えつつ、ゴーギャンはタヒチへと身を潜める。
美しくプリミティブなタヒチの生活の中で、現地の人々と親密な関係を築き、ミューズのような存在となる。だが彼の作品はオリエンタリズムの支配を暴露していく。異国情緒のロマンを自身に宿しつつも、金が尽き、恋人だけでなく雑貨屋の男性からも蔑視の視線を浴びるなか、内なる闇と向き合う。
映画は、タヒチのアトリエと自然の往復を通じてゴーギャンの心象世界を描く。
実際にタヒチ時代に描いた『マナオ・トゥ・パパウ(死霊は見守る、死霊が見ている)』を鑑賞すれば、タヒチのマジック・リアリズムの側面をとらえつつ、死の影を感じさせる作風が浮かび上がる。左側に映るフードを被った女性の不気味さ、死霊が時を待つような視線、その空間に漂う不穏さが凝縮されている。
ゴーギャンが描くタヒチ像は、太陽の下で息づく自然と現地の暮らしが生み出す素朴さに根差しています。彼のタヒチ時代の絵画は、鮮やかな色彩と形の簡素化によって風景と人々の内面を力強く結びつける特徴があります。タヒチの自然は生命力に満ちあふれ、観る者を深く惹きつけます。一方で、ゴーギャン自身の情熱と理想は筆致に素直さと純粋さを添え、作品に独自の奥行きを与えています。私生活では、家族を支えるため画業を離れて肉体労働に従事した時期もありましたが、その経験が絵にさらなる力強さと真摯さを宿らせたとも言われます。
妻がいるのに、画家としての型破りな一面を垣間見られるのは興味深い。しかし、その心にはまだ届かない。
家庭があるのに、画家としての常識を逸脱する一面をのぞかせるのは魅力的だが、その心にはまだ届かない。
家庭がありながら、画家の型破りな瞬間を垣間見せる。魅力的だが、心にはまだ届かない。