1962年1月1日に公開の映画「椿三十郎」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「椿三十郎」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
椿三十郎が視聴できる動画配信サービス
現在「椿三十郎」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「椿三十郎」が配信中です。
| 動画サービスPR | 利用料金 | 視聴 |
|---|---|---|
|
今すぐ見る | |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
椿三十郎のあらすじ
森の闇に包まれた社殿で、九人の若侍たちがひそかに談話していた。次席家老の汚職疑惑を城代家老・睦田に伝えるが、彼は取り合ってくれず、代わりに大目付・菊井の賛同だけを得られたらしい。しかし突然現れた浪人が『菊井こそ黒幕だ』と宣言すると、菊井の手勢が社殿を取り囲み、緊迫した包囲戦へと移っていく…
椿三十郎の詳細情報
「椿三十郎」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
椿三十郎を無料で見る方法は?
「椿三十郎」を無料で視聴するなら、「U-NEXT」「DMM TV」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
椿三十郎のよくある質問
-
Q映画『椿三十郎』のあらすじはどのようなものですか?
-
A
映画『椿三十郎』は、黒澤明が監督した作品で、名刀を持つ浪人・椿三十郎が村を支配しようとする悪党たちから人々を守る物語です。ある日、若侍たちが悪党を追い詰める計画を立てますが、そこへ椿三十郎が現れ、彼らを助けながら事件を解決へと導きます。
-
Q『椿三十郎』での椿三十郎のキャラクターの魅力は何ですか?
-
A
『椿三十郎』の主人公、椿三十郎は、無頼な浪人でありながら人情に篤い人物です。彼の実力や鋭い洞察力、そして人情深い性格が見る者を引きつけ、ただの剣豪以上の魅力を放っています。
-
Q映画『椿三十郎』の制作スタッフについて教えてください。
-
A
映画『椿三十郎』は、黒澤明が監督・脚本を手掛けた作品であり、音楽は佐藤勝が担当しています。撮影には村井博が関わり、黒澤作品らしい緻密な演出と映像美に貢献しています。
-
Q『椿三十郎』のテーマやメッセージは何ですか?
-
A
『椿三十郎』は、義と人情の対立、そして正義とは何かというテーマを描いています。三十郎は、若侍たちの正義感や未熟さに対し、現実的な視点で正しい行動を取ることの重要性を示します。
-
Q原作と映画『椿三十郎』の違いは何ですか?
-
A
映画『椿三十郎』は、山本周五郎の短編小説『日日平安』を基にした作品ですが、映画では原作にはない椿三十郎というキャラクターが中心となります。この創作によって、物語に独自の視点が加わり、よりドラマティックな展開が生まれています。
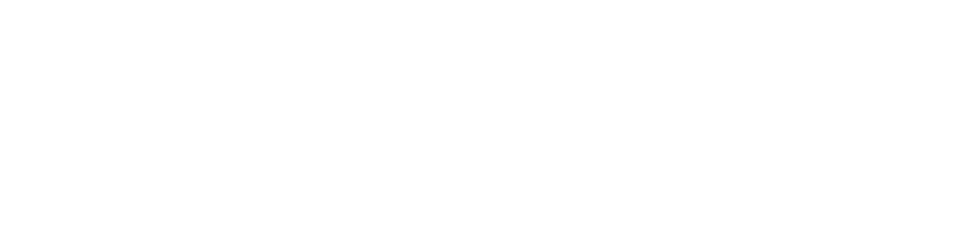
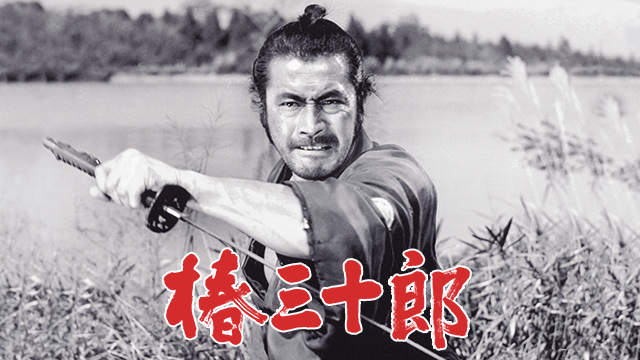
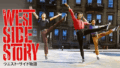
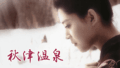
椿三十郎の感想&レビュー
【お前たちの行動は危険すぎて見ていられない】
上役の不正を暴くべく立ち上がる若侍たちを助ける浪人の物語です。
無鉄砲な若侍たちに対して、相手の策略を見抜いた浪人がアドバイスをしながら立ち向かいます。
『用心棒』(1961)の続編的な作品とされていますが、ストーリーには直接の繋がりはありません。
作品全体の雰囲気は明るく、コメディ要素が豊富で、軽く時代劇を楽しみたい時におすすめです!
用心棒よりこちらの方がユーモアに富み、私の好みにぴったり。軽快なチャンバラは観ていて心地よい。故・仲代達也を偲ぶ。
興味深い
理解できないと思ったが、何となく理解できる
無謀に見えるが、しっかり考えている
黒澤明監督の作品を振り返る
社殿内で藩内の汚職を正すべく策を練る若侍九人の前に、殿内奥から浪人が姿を現す。話を聞いたと語る浪人。
脚本:菊島隆三・小国英雄・黒澤明
原作:山本周五郎
久しぶりに見る
浪人と若者たちが汚職を正すまでの物語を、コミカルな空気を交えて描いている。「用心棒」の続編的要素もあるが、独特の雰囲気があり、本作の方が好みだ。
三船の浪人はさまざまな手段を使い、時には暴走する若者たちに計画を阻まれながらも新たな策を講じる。若者たちの成長ドラマとしても描かれ、家老の奥方が「本物の刀は・・」と言うシーンは、無闇な殺生を否定するものとして軽妙ながら深い意味を持つ。彼女の言葉は、彼らにも響いているはずだ。
黒澤にとって特別な思いがある入江たか子が、お姫様として奥方を演じ、捕虜である小林桂樹も滑稽な存在として描かれる。三船三十郎や敵方も含め、人間味あふれるキャラクターたちに、多分心惹かれるのだろう。
私には退屈に感じた「用心棒」も、随分前に観たきりなので、再視聴してみようと思う。
#YAZFILM #MLFILMSYaz #jfilmsyaz #60FilmsYaz
椿屋敷の名はやはり椿そのもの。そんな由来がちょっと微笑ましい️
9人の若侍たちの動きがカルガモの兄弟のようで、思わず吹き出してしまう
組織の腐敗に立ち向かう一匹狼。
体制の腐敗と孤高のヒーローの戦いは、最近の時代劇やアニメ、映画でも頻繁に見られるテーマだ。そのため、この作品に新鮮さを感じることは少ないかもしれない。
しかし、この「型」を確立したのは黒澤明監督だ。従来の時代劇が忠義や仇打ち、浪花節的な要素に主眼を置いていたのに対し、「正義を唱える体制が悪に堕ちたらどうなるのか」や、「権力に溺れる人間の欲望」、「殺し合うことでしか守れぬ正義」といった人間ドラマを映画で初めて描いたのがアキラクロサワの凄さだろう。
詳細は分からなくとも、三船敏郎演じる椿三十郎のカッコよさには圧倒される。名を尋ねられ、庭の椿を見ながら「椿…三十郎」と答えるシーン、その声、表情、仕草、すべてが印象的だ。
特に去り際の姿には、役柄を超えて三船敏郎という男の哀愁と生きざまが滲み出ているように思えた。トシロウミフネ、これぞ真のジャパニーズダンディズムである。
最後の爆発的な出血シーンも強烈だ。血が吹き出る様子はタランティーノの作品を彷彿とさせる。しかし、冷静に振り返ると、「人を斬る」という行為がいかに悲惨で醜いものであるかを訴える怒りのメタファーにも感じる。
痛快で面白く、画の中に10人の侍が美しく収まる構図が秀逸だ。
時折、緊張と緩和のバランスが面白く、好みを外れた部分もあったが、ラストの決闘シーンで血飛沫が豪快に舞い上がり、緊張感のある締めくくりが印象的だった。三船敏郎の「私の名は、、、三十郎。もうすぐ四十郎だけど」といったシリーズが好き。「白髪の七十郎だぜ、おい」というセリフは滑っていて笑ってしまった。
椿の落ちる美しさとその背後にある意味が重なり合って感動的です。十人の若侍たちが一斉に動くシーンの迫力や、カメラの動きが生む空間の広がりは圧巻です。椿三十郎が何度も目を覚ますたびに、カメラのアングルが変わるのも新鮮で楽しめます。そしてラストシーンとその音楽は非常にスタイリッシュです。
ただ、映像やシナリオを含めると、昔見た『用心棒』の方が印象に残っています。また、女親子がいちいち気に障るのは、作品の一部として仕方ないことかもしれません。
『用心棒』(1961年)は、原作「日々平安」(1954年)を意識すると、突っ込みどころが気にならなくなるのが面白いところです。毎回この映画を観た後には新潮文庫を引っ張り出すのが恒例になっているので、次回以降のためにメモしておこうと思います。
– 「もうすぐ四十郎ですが」のシーンでは、三十郎がここまで人を斬る必要はなく、本来のテーマは御家騒動を第三者が頭脳戦で対処することです。
– 高度成長期の日本では、立身出世を求めずに飄々と去っていく三船の姿が成立しています。これは1980年代の大学生が就職を気にせず海外に渡ることができた状況を反映していると思います。つまり、「明日は明日でなんとかなる」と社会全体が考えていたわけです。今の時代、全く想像できないキャリアプランですよね。貧乏はやっぱり厳しいし、国全体が貧しいのはさらに大変です。
– 最終盤の自問自答シークエンスは原作の重要な部分で、そこで明かされる山本周五郎の見識は、現代において論破して「勝った」と誇ることの悲惨さを指摘しています。そんなダサい自分に少しでも寄り添ったことを恥じて、退場するしかないというロジックは、実は古びないものではないでしょうか。本作における三船の行動には、ほんの少しでもそのエッセンスが含まれているように思います。
また、「これはさて 世はさかさまになりにけり 乗た人より 馬が丸顔」という成島柳北の狂歌が伊藤雄之助のセリフとして使われていますが、高杉晋作説がネットに広がっているのには驚きです。IMDbのトリビアには「原作はふたりの浪人の物語」という誤った情報が多くの「いいね」を集めています。このようなデマを否定する仕組みが必要だと感じます。
(そう、黒澤作品に対する感想はだいたいこんな感じになることが多いので、やっぱり『用心棒』の何も言うことがない感じは特に印象的です。)
加山雄三を筆頭に、青年武士と母娘の話し方のリズムが独特だ。全く時代劇らしくない早口と、華族風のたおやかな口調の掛け合いが印象的。そこへ三船の低音が重なり、背後から突然現れる小林桂樹の助言が場の空気を一層賑やかにする。喋っていない場面でも、キャラクターの動きに合わせた音響効果がコミカルで活気に満ちている。アクションの緩急も心地よく、序盤の青年武士たちの疾走を捉えたモンタージュや三船の「30人斬り」といった激しい場面も多い。しかし最大の見せ場は仲代達矢との一騎打ち。沈黙のうちに進む対決は間合いの概念が崩れるかのようで、思わず笑ってしまうほど独創的だった。
コミカルな場面もあり驚きの展開。色彩は控えめながらも、絵作りとして美しい映画。侍たちは素直で愛らしく、見どころがいっぱいだ。