1930年10月24日に公開の映画「西部戦線異状なし」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「西部戦線異状なし」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
西部戦線異状なしが視聴できる動画配信サービス
現在「西部戦線異状なし」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「西部戦線異状なし」が配信中です。
西部戦線異状なしのあらすじ
第一次世界大戦期のドイツでは、盛んに愛国心を説く教師の力強い言葉に心を動かされた学生たちが、次々と軍へ志願した。その中の一人、ポールも例外ではなかった。厳しい訓練を経て前線へ送られた彼が直面したのは、食料の不足と砲弾が飛び交う恐怖の中で、仲間が次々と命を落とす戦争の現実だった。
西部戦線異状なしの詳細情報
「西部戦線異状なし」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 監督 | ルイス・マイルストン |
|---|---|
| 脚本家 | ジョージ・アボット デル・アンドリュース マックスウェル・アンダーソン |
| 出演者 | ウィリアム・ベイクウェル ウォルター・ブラウン・ロジャース ジョン・レイ スリム・サマーヴィル ベリル・マーサー ラッセル・グリーソン リュー・エアーズ ルイス・ウォルハイム レイモンド・グリフィス |
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | アクション ドラマ |
| 制作国 | アメリカ |
| 公開日 | 1930年10月24日 |
| 上映時間 | 136分 |
西部戦線異状なしを見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
西部戦線異状なしを無料で見る方法は?
「西部戦線異状なし」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
西部戦線異状なしのよくある質問
-
Q映画『西部戦線異状なし』のあらすじはどのようなものですか?
-
A
映画『西部戦線異状なし』は、第一次世界大戦の西部戦線を舞台に、新兵たちの過酷な戦場体験を描いています。主に若者の視点を通じて、戦争の無意味さや非人間性を訴えています。主人公パウルが仲間と共に生き残ろうと奮闘する様子が描かれています。
-
Q『西部戦線異状なし』の主人公であるパウルについて教えてください。
-
A
パウルは、『西部戦線異状なし』の主人公で、物語を通じて戦争の恐怖と現実を体験するドイツの若い兵士です。彼は戦場での残酷な経験を通じて、戦争への疑念と虚しさを感じるようになります。
-
Q『西部戦線異状なし』はどのようなテーマを持っていますか?
-
A
『西部戦線異状なし』は、戦争の無意味さや残酷さをテーマにしています。兵士たちの日常や戦闘をリアルに描写することで、戦争の悲惨な現実を訴え、観客に平和の大切さを考えさせる内容になっています。
-
Q『西部戦線異状なし』の制作スタッフについて教えてください。
-
A
『西部戦線異状なし』の監督はエドワード・バーガーで、彼をはじめとするスタッフが第一次世界大戦のリアルな描写を追求しました。美術や衣装にも細部にわたって工夫が凝らされており、臨場感あふれる作品となっています。
-
Q映画『西部戦線異状なし』はどのように評価されていますか?
-
A
映画『西部戦線異状なし』は、戦争のリアルな描写と深いメッセージ性が評価され、多くの視聴者や批評家に支持されています。特に若い兵士たちの心理描写がリアルで、戦争の悲惨さを伝える作品として高く評価されています。



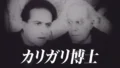

西部戦線異状なしの感想・評価
世間の話題と前線の実態の乖離を巧みに描く反戦映画だ。パリへの侵攻を促す大人たちに呆れるポールの場面が特に印象的で、このような反戦映画が作られていたにもかかわらず第二次世界大戦が起きてしまったのは残念だ。原題 All Quiet on the Western Front(西部戦線異状なし)のラストの描写は見事に回収され、非常にまとまりのある名作だと思う。ただし quiet(静寂)が死を連想させる意味を持つ点はあまりにも残酷だ。
故郷と共に生きた家族
無名の点で兄弟と共に死ぬ
挟まれた心はやがて擦り切れてしまう
この作品はWW1後に制作されたが、厭戦のプロパガンダとしての役割を果たすことはなかった
一部に過ぎなかったからこそ。時計仕掛けの歯車でもなかったから。
幕間はこれから。二部はその後に続く。
小学生の頃に読んだ『まんが世界の歴史』で本作のシーンがオマージュされていたことを強烈に記憶している。それは何気ないワンカットで、一人の人間の死を描いたものだ。
戦争が英雄のいない戦争に変わってしまったことを示す衝撃的な瞬間を私は忘れることができなかった。
第一次世界大戦を背景にしたドイツの物語。
一人の老教師が教室で愛国心を熱く語り、生徒たちを戦争に志願させようとする。彼は巧みにクラスメートを兵士に送り込んでしまう。
新兵教育に現れたのは、以前知っていた男。しかし、軍隊では彼はもはや、のんびりとした郵便局員ではなかった。
そして彼らは戦場に向かい、当然のように仲間が次々と命を落としていく。地獄のような日々を送り続ける。
日本でもかつての戦争において、軍国主義教育に加担し、多くの教え子を戦場に送り出してしまった教師がいたのだろう。「罪」を背負って生きていたのかもしれない。
これまでいくつかの反戦映画を観たが、共通してやりきれない気持ちが残る。
今なお戦争が続く現実。戦争の根源は、人類の永遠のテーマなのかもしれない。
幼少期に録画して何度も観たが、ラストシーン以外の内容はすっかり忘れていた。
100年前の作品だから古さを感じるかと思ったが、全くその印象はなかった。長い作品だが、無駄なカットは一切存在しない。
冒頭では教師が「戦争に行け」と無責任に煽り、生徒たちが狂気の笑顔で浮かれていくシーンが非常に印象的で… 一生忘れられないだろう。
あのシーンは、今でも残念ながら通用しており、SNSやYouTubeで勇ましい言葉に感動して熱狂する人々と重なって見えてしまう。
古いモノクロ映画だが、内容には全く古さを感じさせない作品だ。
古いモノクロ映画ながら、物語の中身は現代にも通じる新鮮さを保っている。
古さを感じさせないストーリーを持つ、昔ながらのモノクロ映画。
古いモノクロ映画でも、内容は現在にも訴求力を持つ作品だ。
古いモノクロ映画だが、時代を超えて普遍的な魅力を放つ作品。
描写が緻密な戦争映画。塹壕戦では敵兵が次々と押し寄せ、ひとたび塹壕に到達すれば、内部で絡み合いながらの激しい戦闘が展開される。装備の描写も印象的だ。安全な場所での老人たちがチェスの棋譜のように戦術を白熱して語り合う場面は、戦場の現実と理論の距離を強く感じさせる。主人公は最後、束の間の夢を見たいと願ったのだろうか。現代の戦争映画は音楽も含めて重苦しくなりがちだが、モノクロの単調さが逆に効果を生んでいる。これはドイツ視点の作品だが、制作はアメリカ映画である。
– モロクロであることに支障はなく、むしろ感覚が研ぎ澄まされて没入感がさらに高まりました。
– モロクロであることに何ら支障はなく、感覚は一段と研ぎ澄まされ、没入感が増大しました。
– モロクロであることに問題はなく、感覚が鋭くなり、没入感が深まりました。
おすすめされて視聴しました。悲しかったです。最初はみんなで楽しく過ごしていたのに、戦いが始まると次々と仲間が死んでいく これが100年前の映画こうした作品が存在しているのに、人は未だに戦争を繰り返しているなんて。ブーツをもらった子は、いつもよりも動きが良くて前に出過ぎてしまったのかなと考えてしまいました。最後のおじさんが亡くなるシーンも耐え難かったです(ヽ´ω`) 主人公の結末ももう涙が止まりません Netflix版も観たいので、加入後に見ようと思います。
第一次世界大戦に従軍した作者の体験を基にしたこの映画は、作品に登場するエピソードがリアリティに溢れている。教師の演説に洗脳される学生たちの姿から、戦場で蝶に触れようとした主人公が狙撃されるまで、反戦映画に必要な要素が全て揃っている。戦争を舞台にした映画が反戦を描く上で、避けて通れない作品といえる。
元郵便配達が鬼軍曹となり新兵を鍛える訓練のシーンは、戦争映画の定番となり、酒と女で緊張を和らげる瞬間も欠かせない。砲弾が飛び交う中、敵軍が味方の塹壕に突入し、鉄条網の前で次々に機銃掃射されていく長回しのシーンは、『プライベート・ライアン』を思わせる圧倒的な迫力を生み出し、「殺伐」とした描写がよく表現されている。主人公は老人が始めた戦争で若者が犠牲となる状況を嘆き、療養休暇で戻った故郷には居場所がない。ここには『ジョニーは戦場に行った』と同じテーマが見受けられる。
1930年制作のこの映画は、その映像技術はさておき、内容は今も色あせることがない。第一次世界大戦から第二次世界大戦、ベトナム、イラクへと舞台が移り変わっても、結局残るのは犠牲の兵士たちの屍と虚しさだけだ。誰のため、何のために戦っているのか?兵士たちは銃を握りながら自問を続ける。
かつて誰も経験したことのない規模の世界大戦。この戦争は誇張ではなく、世界を根本的に変えてしまった。この作品が第一次大戦と第二次大戦の間に制作されたことは非常に興味深い。制作者が第一次大戦の悲惨さを訴えつつ、再び大戦へと向かいつつある国際情勢に警鐘を鳴らしていることが感じ取れる。
塹壕戦の戦いの様子が詳細に描かれており、一度奪われた陣地を取り戻す描写が存在する。雨の中を行軍する軍隊を、室内からドア越しに撮影したショットは、隊列と降り注ぐ雨が織り成す情景を捉えている。
戦争は人を変えてしまうものだが、正確には戦争に従事した人々が自分の居場所を失ってしまうということだ。生き残ったとしても、その心は閉ざされているため、再び自らの居場所を見つけられず、結局は再び戦地へ向かわせてしまうのだ。
『西部戦線異状なし』
原題: All Quiet on the Western Front
製作配給: ユニバーサル映画
1930年(昭和5年)
(Amazonプライム・ビデオ)
教師「君たちにとって戦争は貴重な経験になる。軍服を着ろ。名誉から逃げるのか?自らを高めよ。戦いは美徳であって軽蔑されるべきではない。戦争には犠牲が伴うこともある。だからこそ、ラテンの格言を思い出せ。トロヤ戦争の際、ローマの兵士が口にした『祖国に捧げる死は甘美である』。今、祖国が君たちを呼んでいる。栄光が今始まるのだ。名誉の地が待っている!」
「これまでの知識を忘れ、自分の未来など考えるな。おまえたちは兵士になるのだ。立派な人間に育ててやる。一人前にならなければ、死が待っている。よし、気をつけ!」
「なぜ戦争は始まったのか?国が国を侮辱したからだ。」
「どうやって?ドイツの山がフランスの平野に怒りを抱くのか?」
「戦争が始まるときには広場にロープを張り、王や政治家や将軍を下着姿で棍棒で戦わせればいい。そして勝者を決めるのだ。」
ポウル「先生は今でも多くの若者を扇動している。祖国に命を捧げるのが善だと。しかし、最初の爆撃で気づいた。命を犠牲にしてまで祖国のために戦う必要はない。どれほどの人が命を失ったのか。あなたは命を捨てろと言うが、自分にはできるのか?」
朝ドラ『あんぱん』に登場する八木の戦時中のエピソード(敵を刺殺後に敵兵の持っていた家族の写真を見つける)がこの映画と同じだと感じた。『あんぱん』の脚本家が盗作したとは思わないが、戦時中には多くの似た出来事があったのだ。敵兵も誰かの息子であり、夫であり、恋人であり、父親なのだ。
敵兵は鬼や悪魔ではなく、同じように両親から生まれた人間であり、家族が存在する。
戦争とは、同じ人間同士が理由もなく命を奪い合うことである。
2022年版のNetflix制作を先に観ていたため、かなりの違いを感じた。
1930年版
・教師に扇動され志願
・新兵訓練
・戦場
・休暇。フランス女性との交流
・再び戦場。フランス兵を殺害
・休暇で帰郷。扇動教師と対決
・再び戦場へ
・終幕
2022年版
・戦場から始まる
・戦場
・休暇。女性との交流なし
・戦場。フランス兵を殺害
・将軍たちが停戦交渉
・終幕
1930年版は扇動的な教師に反発するシーンがあるため、ナチス支配下のドイツでは上映禁止になった。
教師に煽られ、勢いで志願した兵士が不条理な訓練を受け、常に空腹の戦場で友を失い、人を殺すことになってしまう。レマルク自身の実体験、そしてスタッフの多くが戦争を経験していたため、戦場の描写は非常にリアルで、ただ胸が痛む。
2022年版は「何も知らない若者の変貌」という核が欠けており、ありふれた戦争映画に終わってしまっている。主人公に感情移入しづらく、最終的に「お前は誰だ?どんな人間なのか?」という印象が残る。
プーチンが「ウクライナは元々ロシアのものだ」と侵略し、ネタニエフが「パレスチナを地上から抹殺する」と大量殺人を続ける2025年の昨今。
政治家は若者を扇動し、訓練と称して連れ出し、お金を払って雇い、戦場へ送り込み、子どもたちが飢えたり殺されたりしている。
95年前の映画がすでに示しているのに、世界は進歩していない。
・戦場から帰った兵士が故郷の人々に感じる違和感。これは『アルマジロ』や『ハート・ロッカー』にも共通する部分がある。銃後の人々は真実の世界を知らないのだ。
・食糧調達を担当する古参兵カッツの本名はStanislaus Katczinsky。ポーランド人名である。当時ポーランドにあたる国土はロシア、プロイセン、オーストリア=ハンガリー帝国に分割されていたため、カッツはプロイセン地域から徴兵されていたのであろう。
・クレーンカメラによる高所からの戦場の描写。移動撮影のスケールが非常に大きい。
・塹壕の中でひたすら砲撃に耐え続ける描写は、神経を蝕まれる様子が生々しかった。
あらすじ
第一次世界大戦を背景に、ドイツの少年たちが教師の扇動で兵士として志願するところから物語は始まる。主人公ポールをはじめ生徒たちは、軍内部の階級や戦場の過酷さに直面し、心身ともに追い詰められていく。
感想
戦争の現実と意味を問い直す若者たちの姿が強く印象に残る。特にポールが戦場で経験する苦悩と成長の過程が心に響く。
ストーリー展開の見どころ
– 前半は血気盛んな若者たちが志願し、訓練を受ける場面。学生気分が抜けず、ユーモラスな場面も混在する。
– 戦場に出てからは現実の過酷さが露呈し、彼らの価値観が揺らぐ。
– 物語終盤には、戦場と故郷・国にいる人々との温度差を痛感する場面が描かれる。
映像表現と臨場感
– 中盤の戦闘シーンは長く続くが、モノクロ映像と画質の劣化が戦場のリアリティを際立たせる。古さを感じつつもスケール感が伝わる。
主人公ポールと仲間たち
– ポールは優しく仲間思いな人物として感情移入しやすい。彼の心情は一つひとつの経験に丁寧に寄り添い、観客の疑問と結びつく。
– 仲間や先輩兵士も個性豊かで、ささいなやりとりにも味があり、物語に緩急を与える。戦争だからこその緊張感と、戦時下にも見える明るさがバランスよく描かれている。
テーマと余韻
– 戦場の暴力と孤独、若者の命の消耗、国の未来を脅す状況を象徴するラストが心に刺さる。
総評
– 視聴のしやすさと戦争の悲惨さを両立させた秀作。力強いメッセージ性とエンターテインメント性のバランスが高く評価できる。
鑑賞日と視聴方法
– 2025年8月15日、Amazon Prime Videoで鑑賞
過去から現在にかけて戦争が絶えず、残酷な歴史が存在することを考えると、気持ちが沈んでしまいます。人間に生まれたことに申し訳なく感じる瞬間もあります。
高校の世界史で知ったことが印象に残っていたので、選んでみた。現在、映画は3作作られているようだが、やはり最初の作品が最も優れていることが多い。第一次世界大戦を舞台に、熱烈な扇動に煽られる若者の視点から、兵士たちに国家を背負わせる傲慢さや戦争の虚しさを描写している。
冒頭の学校のシーンで、教師が男子生徒に激励する場面が印象的で、ここでの大義名分は、最近YouTubeで見たロシアのウクライナ侵攻に関するインタビューに登場した年配の男性が「若者はロシアのために戦うべきだ」と語る内容に重なった。無責任な者が、いつの時代も特に犠牲となる人々を駆り立てるのだなと感じた。
若者たちは大人にそそのかされて期待を胸に入隊するが、すぐに偉そうな大人たちに扱われ始める。かつて朗らかだった郵便配達夫は、軍の鬼として支配欲に耽っていた。この点が別の教官を出さずにまとめているところが良かった。
初めての戦死を目撃し、飢えと戦い、戦場の騒音や振動で精神的に疲弊していく様子が淡々と描かれていた。「銃と軍服を脱いだら友達になれたのに」という嘆きは、どの時代にも存在するのだと感じた。殺したフランス兵の軍務手帳から家族の写真が出てくると、モブ兵士が具体的な人物として浮かび上がり、若いドイツ兵にとって殺人の現実が生々しく感じられる。
帰郷しても無責任な年寄りたちの軍事論を酒場で聞かされ、学校では恩師が再び出征を煽る様子に、老いた母の胸で涙を流すのも理解できる。美しく純粋な生の象徴である蝶を追い求め、この若者が命を奪われても戦争は止まることなく、生き残った者たちは去って行く。
散々使われ、敵味方問わず傷ついても「異常なし」とされるのは、兵士が国家の争いの駒に過ぎないからだ。これはどの時代の戦争でも同様だ。クレムリンで優雅に暮らすロシア高官にとって、ウクライナの戦場で命を落とす若者がいても、状況は変わらない。
モノクロ映画の独特なドキュメント風の演出もリアリティがあり、良かった。字幕版で視聴し、原作小説や作者に関する研究もしたい。もし時間があれば、リメイク作品も見比べてみるのも面白いかもしれない。
—国家のために教育を受けた若者が赴いた戦地は、残酷な現実が待ち受けていました。仲間は次々と撃たれ、足を失い、眼球が有刺鉄線に引っかかりネズミがかじったパンを口にし、泥水で手を洗う日々を送る前線の現実を知らずに、国民国家としての従軍を教育され続ける少年たち。その行く先は—
国民全体が洗脳されている様子が描かれており、その呪縛を解くには死を感じるしかないという厳しい状況が浮き彫りになります。反戦映画でありながら、この数年後に第二次世界大戦が勃発するという皮肉には何とも言えない虚しさがあります。
大規模な戦争はもう起こらないだろうという過信が、国同士のコミュニケーション不足を助長し、大惨事を引き起こす要因となってしまいます。その油断は現代にも見られるのではないでしょうか。
この映画から得られる教訓は多岐にわたります。