2025年1月10日に公開の映画「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男が視聴できる動画配信サービス
現在「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」が配信中です。
MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男のあらすじ
雪に閉ざされた新潟県十日町で、ティーンエイジャーの桜井昭夫はヘッドフォンとレッド・ツェッペリンのレコードの山に囲まれ、自室に閉じこもっていた。その後、東京へ移り住んだ昭夫は、昼は着物のセールスマンとして働き、夜はジミー・ペイジのギター・テクニックとカリスマ性を徹底的に身につけた「Mr.Jimmy」桜井としての顔を手に入れる。35年間、東京の小さなクラブでツェッペリンのビンテージ・コンサートを一音一音再現してきた彼だが、ある夜“本物”のジミー・ペイジが演奏会場に現れる。その瞬間、彼の人生は永遠に変わる。ペイジの喝采に触発され、昭夫はサラリーマンの安定を捨て、家族を置いてロサンゼルスへ渡り、コピーバンド“Led Zepagain”に加入する。しかし、やがてバンド内の方向性の違いが対立を生み、彼が思い描く理想のアメリカと現実が交錯していく。
MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男の詳細情報
「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 監督 | ピーター・マイケル・ダウド |
|---|---|
| 出演者 | ジミー桜井 |
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | ドキュメンタリー |
| 制作国 | アメリカ 日本 |
| 公開日 | 2025年1月10日 |
| 上映時間 | 114分 |
MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男の公式PVや予告編動画
「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男を見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男を無料で見る方法は?
「MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。




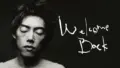

MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男の感想・評価
学生時代から様々なブートを研究している凄腕のコピーバンドが登場するギタリストのドキュメンタリー。日本のロックに焦点を当てた映画としても非常に興味深い。
感動的なドキュメンタリー映画。
本作を観るまでは、主人公のジミー桜井について知りませんでした。そのため、初めは彼がモノマネ芸人かと思っていましたが、鑑賞後にはそれ以上の存在であることが分かりました。
アーティスト自身による過去作へのトリビュートライブはよく見られますが、ジミー桜井はそうした部外者として、LED ZEPPELIN、特にジミー・ペイジの演奏や衣装を徹底的に再現しています。彼の取り組みは、信仰心や情熱と言えるでしょう。
日本にはLED ZEPPELINの楽曲を模倣したバンドもいますが、私の好みには合いません。しかし、ジミー桜井はまったく別です。彼はジミー・ペイジの信者であり、自身の表現は再現性と精度に凝縮されています。演奏の質はもちろんのこと、彼の動きや衣装も素晴らしく、思わず笑顔になったり、感動したり、目が離せません。
ジミー桜井は、トリビュートバンドとしてビジネスである以上、観客に受け入れられないといけないという他のメンバーとぶつかることが多く、彼の活動やメンバーは流動的です。頑固な職人なのか、またはこの道一筋の研究者であるか、真似できない存在ですが、私は彼を全面的に支持します。
ジミー・ペイジが他人のライブを通して観ることは非常に少ない中、彼はジミー桜井の演奏を最後まで観て(狭い会場で、一般の観客の中で)、満面の笑みで写真に映っている姿が印象的です。素晴らしい瞬間です。
本作を観て、LED ZEPPELINが今でもアメリカで人気であることを実感しました。ただ、日本のZEPファンは洋楽やハードロックに対しインテリ気質な傾向を感じますが、アメリカのジミー桜井の演奏を観に来る人々は、音楽と共に楽しい時間を過ごすことを求めているように思えました。これは音楽への向き合い方の違いなのかもしれません。
2025年8月 U-NEXTで視聴
推し活を極める最高峰の体験。ひとりの男性を追い続け、映画化まで実現した希少なストーリー。激レアさんの中でも抜群の話題性を放つ逸話です。
昨夜公開された『Becoming Led Zeppelin』を、興奮が冷めないうちに観た。
この人のことを知ったのはつい最近だ。[cinnamon]のライブも観に行った。完コピバンドとしてはcinnamonが一番完成度が高いと思っていたが、この人のこだわりも凄い。ジミー桜井さんの完コピへの情熱と信念は、決して揺らがない。
その分、ほかのバンドのメンバーはZEPPELINが好きでも、完コピを貫くのは自分たちの考えと違うのかもしれないと、想像させる。
たまに六本木のアビーロードというビートルズのコピーバンドの店へ行くが、そこは単なるコピーバンドというより、さまざまなアレンジを加えて自分たちの曲にしているのが聴いていてとても楽しい。
他のバンドメンバーも同じ方向性で、人気のある曲でオーディエンスを楽しませたいという狙いがあるのだろう。
Led Zeppelinはライブ・バンドだから、ジミー桜井さんのこだわりもよく伝わる。私もブートのライブ盤を何枚か手元に置いているが、1973年頃のロサンゼルス公演の『Bring It On Home』でのロバート・プラントがハーモニカをソロで吹きまくるのが格好良すぎて、最後にアンプを蹴飛ばす音まで収録されていた。
ペイジは、『幻惑されて』や『胸いっぱいの愛を』の速弾きよりも、スローなテンポに転調する場面が好きだ。シンプルなメロディながら、実に格好いい。
映画の話題に戻ると、中盤でジミー・ペイジ本人が訪れて観客へ語りかける場面が、この作品の最大の盛り上がりだったと思う。あのタイミングで見せた演出は良かったと思うし、ペイジのインタビューがあればさらに良かったかもしれない。
ジミー桜井さんと同じ思いを共有する人たちと、これからもずっとバンドを続けてほしい。
この人のことを初めて耳にしたのはいつだったろう。ずいぶん前のことだと思う。ツェッペリンの曲を完コピし、スタジオ録音盤だけでなく各ライブ演奏までも再現すると聞いた日本人ギタリストがいるそんな話をどこかで耳にした記憶がある。
それが、この人、ジミー桜井だったのだ。
私は若い頃、ツェッペリンとジミー・ペイジに強く魅了されたひとりだった。レス・ポール・スタンダードを愛用し、EDS-1275、いわゆるSGダブルネックもペイジに憧れて買い、今でも手元にある。
ZEPの曲も多くコピーした。もちろん私も多くのファンと同じく、スタジオ・テイクのコピーを主にしてきた。ただし、MSGバージョンとして語られる「狂熱のライブ」に収録された「ロックンロール」と「天国の階段」も、桜井さんと同じくコピーしている。ZEPはスタジオとライブで全く異なるのが常だから、この2曲はMSG版も含めて再現したのだ。ペイジ・ファンの中には「自分もMSG版を弾ける」という人が多いだろう。それだけ魅力的で真似してみたくなる曲だ。
だから、ジミー桜井さんの気持ちはよく分かる。初めてZEPを聴いたときの衝撃、初めて「狂熱のライブ」を観たときの感動は、私も若い頃に経験した同じものだ。
ただ、この人は過剰に幻惑されてしまった側面がある。
ドキュメンタリーの中には「普通じゃない人に密着する」タイプがあるが、桜井さんの過剰ぶりは見ていて圧倒される。からかっているつもりはない。素直に驚くし、時には感動さえ覚える。自分にはできないことを成しえている人への敬意でもある。
よくバンドが解散したりメンバーが抜けたりする時には「音楽性の違い」と言われることがある。桜井さんも何度かメンバーチェンジや解散を経験するが、このケースほど原因が明確に感じられる例は珍しい。観客の多くが「そうなるよね」と納得するはずだ。
それはもう「音楽性の違い」以上の、本質的な方向性の差だ。彼が目指しているのはレッド・ツェッペリン道つまり道(タオ)だ。桜井さんを形容するなら「ジミー・ペイジという職業についた男」と言うほかない。
要するに彼は、古典芸能としての「レッド・ツェッペリン」を継承する者なのだ。他にこの方向を公言できる人はほとんどいない。いまの時代で仮に誰かと組んでも、うまくいくとは限らない。
落語家が師匠の話芸を自分流にアレンジすることはあるが、桜井さんの思考にはそれが禁忌。完全な原理主義者というべきだ。だから他のメンバーは呆れたり、うんざりしたりするのも無理はない。
映画の終盤、彼はボンゾの息子ジェイソン・ボーナムと出会い、「狂熱のライブ」にもその幼い姿が映っていたジェイソンと結びつき、バンドに加わる。これがいちばん幸せな形なのではないかと私は思う。
私は歴史に詳しくないので具体例を挙げられずに悔しいが、戦国時代の理想的な治世を復興しようとする武将が強権的すぎて部下がついてこないとき、かつての将軍の落胤が現れてそれを擁立し、右腕となって秩序を取り戻していくそんな構図に似ている。正統な血を受け継ぐ殿でなければ暴走は抑えられない。そしてその殿には絶対服従するだろう。
繰り返すが、私は桜井さんをからかっているわけではない。彼が苦しむ人生を選んだのだと、ただ嘆息しているのだ。求道者という生き方は確かに生きづらい。
それでも、あの瞬間だけは彼の人生が報われて見えた。ジミー・ペイジがライブを観に来ていた、というあの瞬間だ。映像にもペイジがカメラの端に映っている。”Since Ive Been Loving You” のイントロで、ライブ版の即興から一呼吸おいて曲が流れ込む瞬間、私がリズムに合わせてうなずくと、ペイジ本人も客席で同じ仕草をしていたその場面には心を動かされた。神がその曲に乗ってくれたようで、私ですら少し泣きそうになった。ジミー・ペイジはライブの終わりに誰よりも早く立ち上がって拍手を送っていた。
しかし、この作品を見ていて私が感じたモヤモヤは残る。Led Zeppelin のライブは基本的にスタジオの再現ではなく、即興とアドリブだらけだ。前もって何小節で、どのタイミングで合図とするそんな段取りはあるのかもしれないが、10回演奏したら10回とも全く違う。「その場の即興性」を重視していたはずだ。
その即興性をすべて完コピしてしまう意味はどこにあるのか私はずっと考え続けた。ただ、意味がないと言っているのではない。きっと意味はある。けれど観終わっても私の答えは見つからない。
ちなみに私より少し年下の私が80年代にZEPにはまったとき、三大ギタリストとして神格化されつつも「ジミー・ペイジはそんなに巧くない」という視点も同時にあった。ペイジのミスタッチが多いことも当たり前のように語られていた。技術だけで神格化されたわけではない、というのが当時の実感だった。ペイジのセンスこそが聴く者を魅了する理由だった。
だからこの作品を観て、私は「桜井さんはペイジのコピーがうまいな」とは思うが、「ギターが上手い人だな」とは感じなかった。あくまで継承者としての自認が強いからだろう。
ガス・ヴァン・サントの『サイコ』のような人物像にはあまり共鳴しなかったが、彼の生き方には別種の敬意を覚えた。
そういえば、ヒッチコックが生きていたらどんな映画を作っただろうそんな想像が頭をよぎる。新しい映画技術はこの数十年で数多く生まれている。CGやVFXをどう活用するか、作り手としての選択肢は広がっている。
この作品の演奏はやはり「古い」感触を否めなかった。悲しく、残念にも感じるが、それは私の感じ方でしかない。桜井さんはラ・ラ・ランドのセブのような人なのだと感じた。
そう考えると、桜井さんはジミー・ペイジが生きていたらどう演奏しただろうという問いに対して、ひとつの答えを探し続けるべきなのかもしれない。あっ、ペイジよ、ごめん。お前は死んでいなかったんだという結末で締めくくるのもひとつのユーモアだとしても、2000年の来日公演を楽しみにしていた私のチケットは、彼の椎間板ヘルニアのせいでキャンセルになってしまったのだった。
【書きかけ】面白かったー。(*´ω`*) ペイジが現れる瞬間、確かに何度も見ましたよ、桜井さん!
オタクの中でも自らクリエイターになり、推しと同じフィールドで活動する(推しとの同一化)、その上、推し自身が直に認めるような表現の高みに達している これは非常に稀なケースだと思いました。
また、これほど熱心なマニアでありながら、その生き様について自他が語る際に「宗教」という言葉がほとんど使われていないことに気づきました。もしこれが「オタク」(漫画・アニメ・ゲームなどのマニアックなジャンル)であれば、その議論には躊躇せず、頻繁に宗教的な語彙が用いられることでしょう。
昔、影響を受けたアーティストの服装を真似ていたことがあるので、その気持ちはよくわかります。歳を重ねても、情熱を持ち続け、約40年も変わらず活動しているのは本当に素晴らしいし、ただただ敬服します。(ジミー桜井は年代別に3種類のリフを弾き分けていましたが、ジミーペイジ本人はそれを忘れているかもしれませんね。)
奥さんの後押しを受けて会社を辞め、アメリカに渡ったジミー桜井。ビジネスにこだわらない彼とメンバーとの間に意見の相違があったり、途中加入したクワイエットライオットのドラマーやマネージャーに関しても言えることですが、彼らはすでに成功を収めており、「昔の大好きなツェッペリンを追い求める」ための趣味のように見えました。
ジミー・ペイジは ZEPファンがまず視るべき存在だ。突き抜けた生き方にはただ敬意を表します。継続は力なり。コピーに徹底してこそ見えてくるオリジナリティなのかもしれません。結局、彼は唯一無二の存在だからです。
ツェッペリンをリアルタイムで体験できなかった世代も、体験した世代も、彼は必須のミュージシャンと言えるのではないでしょうか。なぜなら、そのころを味わえる機会を提供してくれるからです。
ものまねミュージシャンと侮るなかれ。彼はそのものに近づいた、稀有な人物です。素晴らしい。
ただ、映像作品としてはやや凡庸だった印象。彼の存在報告や活動報告といった内容にとどまってしまった感が否めません。
【ストーリー】1.0
【映像】3.0
【キャスト】1.0
【音楽】3.0
この映画を観て感じたのは、あくまで私個人の感想です。
このジミー桜井氏は、一緒に過ごしたら必ず衝突するタイプだと強く感じました。
確かにジミー・ペイジへのこだわりは尊敬に値しますが、それを自分の中に留め、周囲に押し付けるべきではないと思います。
レッド・ツェッペリンのヴォーカルが語っていた言葉「彼がジミー・ペイジなら何を言っても、何を求めてもいい。しかし彼はジミー・ペイジではなく、私たちはレッド・ツェッペリンではない」この考えが、すべてを象徴しているように感じました。
例えるなら、熱心すぎる鉄道オタクが「最高の写真を撮るためには線路に入るべきだ」と主張するような危うさがあります。
映画自体は不快感を残す作品でしたが、レッド・ツェッペリンの映像表現と実在のジミー・ペイジの登場シーンだけは、点数を少しだけ上げる要因になりました。
映画『エフワン』を観た後、レッド・ツェッペリンの音楽が聴きたくなり、『レッド・ツェッペリン / 熱狂のライブ』を探していたところ、偶然見つけたドキュメンタリーを鑑賞しました。
再現芸術というジャンルをご存じでしょうか?私自身も初めて聞く言葉でした。
ジミー桜井氏のジミー・ペイジへの愛情はただの物真似を超えており、彼の情熱はまさに偏執的です。このような情熱的な人物を観ることこそ、ドキュメンタリー映画の魅力です。
再現は視覚的なコピーにとどまらず、その演奏を忠実に再現しつつ、ビジュアルにも徹底的にこだわる姿勢が美しいです。
例えば、特定の演奏日を再現するだけでなく、その際に使われたギターやアンプ、その他の機材はもちろん、当時の衣服までも再現します。衣服に関しては、腕を曲げた際の皺まで再現するよう服飾デザイナーに注文するという徹底ぶりです。
さらには、本物のジミー・ペイジが彼の演奏を聴きに訪れ、認められるというのも驚きです。
ギターのピックアップだけでなく、ビルダーと相談しながらピックアップカバーも再現し、ギターアンプの回路のハンダまでこだわります。
レッド・ツェッペリンは4人組のバンドなので、周囲のメンバーも大変ですね。
このドキュメンタリーは、優れた贋作や本物に近い偽札に類似する(合法的な)再現芸術を目の当たりにできる、愛に溢れた非常に貴重な作品です。