1993年8月7日に公開の映画「機動警察パトレイバー2 the Movie」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「機動警察パトレイバー2 the Movie」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
機動警察パトレイバー2 the Movieが視聴できる動画配信サービス
現在「機動警察パトレイバー2 the Movie」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「機動警察パトレイバー2 the Movie」が配信中です。
機動警察パトレイバー2 the Movieのあらすじ
2002年冬。横浜ベイブリッジに謎のミサイルが投下される…。報道ではそれが自衛隊機によるものだと伝えられるが、実際には該当する機体は存在していなかった。この事件を契機に続発する騒動は、警察と自衛隊の対立を引き起こし、政府は事態の深刻さを認識して実戦部隊を治安出動させることに。恐るべきテロリストが東京で再現した<戦争>を追い、第2小隊の最後の出撃が始まった!
機動警察パトレイバー2 the Movieの詳細情報
「機動警察パトレイバー2 the Movie」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
機動警察パトレイバー2 the Movieの楽曲
「機動警察パトレイバー2 the Movie」の主題歌や挿入歌、サウンドトラックを紹介します。映像だけでなく音楽からも作品の世界を感じてみましょう。
- サウンドトラックPatlabor 2 - The Movie (Original Soundtrack) Kenji Kawai
機動警察パトレイバー2 the Movieを見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
DMM TV

- 新作アニメ見放題配信数がトップクラス
- 業界最安クラスの月額料金
DMM TVは、DMMグループが提供する動画配信サービスで、「DMMプレミアム」に加入することで見放題作品を楽しめます。
配信作品数は20万本以上。アニメ・特撮・2.5次元舞台作品に強く、新作アニメの先行配信数は業界トップクラス。放送後すぐに最新アニメを視聴できる点は、アニメファンにとって大きな魅力です。さらに、DMM TV独占のドラマやオリジナルバラエティも充実しています。
月額料金は業界最安クラスの550円(税込)。14日間の無料体験に加え、新規登録で550円分のDMMポイントがもらえるキャンペーンも実施中です。コスパ重視で動画配信サービスを選びたい方におすすめのサービスです。
機動警察パトレイバー2 the Movieを無料で見る方法は?
「機動警察パトレイバー2 the Movie」を視聴するなら、「U-NEXT」「DMM TV」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
機動警察パトレイバー2 the Movieのよくある質問
-
Q『機動警察パトレイバー2 the Movie』のあらすじはどのようなものですか?
-
A
『機動警察パトレイバー2 the Movie』は、近未来の東京を舞台にした作品で、謎のテロ事件をきっかけに自衛隊と警察の対立が描かれます。主人公たちが所属する特車二課は、この混乱の中で真実を追求し、事件の黒幕を突き止めようとします。軍事的な要素とミステリーが組み合わさったストーリーです。
-
Q『機動警察パトレイバー2 the Movie』のメインキャラクターについて教えてください。
-
A
この映画の主なキャラクターには、元特車二課の指揮官・後藤喜一と、新たに特車二課に加わった南雲しのぶがいます。彼らは複雑な状況下での判断を迫られ、過去の選択と向き合います。それぞれの成長と葛藤が描かれた作品です。
-
Q『機動警察パトレイバー2 the Movie』のテーマは何ですか?
-
A
この映画のテーマは、戦争と平和、そして情報操作といった現代的な問題を取り上げています。特に、政治やメディアの影響力が個人の行動や信念にどのように影響を及ぼすかが深く考察されています。監督の押井守が提示する社会的メッセージが強い印象を残します。
-
Q『機動警察パトレイバー2 the Movie』の製作に関わった重要なスタッフは誰ですか?
-
A
『機動警察パトレイバー2 the Movie』は、押井守が監督を務め、脚本は伊藤和典が担当しました。さらに、音楽は川井憲次が手掛け、重厚な雰囲気を演出しています。この映画の映像美と音楽は高く評価されています。
-
Q『機動警察パトレイバー2 the Movie』と原作との違いについて説明してください。
-
A
映画『機動警察パトレイバー2 the Movie』は、原作のマンガやOVAシリーズを基にしつつも、独立したストーリーとして展開されています。よりシリアスで政治的な内容が強調されており、娯楽性だけでなく社会性を追求する姿勢が際立っています。
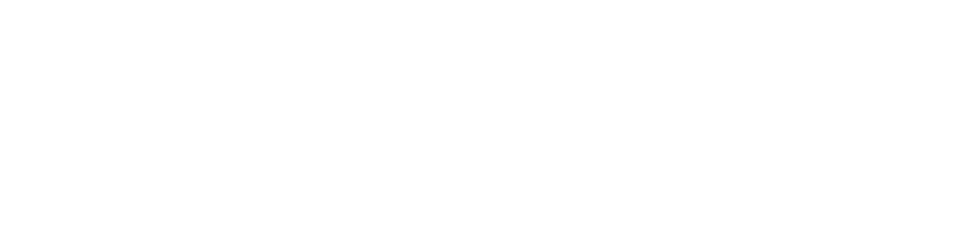






機動警察パトレイバー2 the Movieの感想・評価
戦争の恐怖を静かな筆致で伝える秀作。静かなのに怖さが強い。構図が魅力的で、ひとコマが絵になる。物語は何度も観ないと全体を理解しきれないところがまた良い。特車二課の面々が大好きだ。
30年以上前にこんな作品が作られていたこと自体が驚きだ。1作目よりも暗く難解で、全てを理解できたわけではないが、切り取る場面のどこを取っても絵になる渋さが際立つ。楽しめたかどうかは微妙だったものの、観て良かったと思える作品だった。
言葉を交えなくても、絡み合う指先からあふれ出す感情の瞬間を描く名シーンは、初めて観たときに強く心に刻まれ、今もなお忘れられない。何度も見返す価値がある秀作で、劇伴も必聴だ。
前作に続き、押井監督が手掛ける。だから安心してご覧ください。
冒頭から、すっかり仕事に慣れ先輩として成長した太田たちに置いていかれたような孤独感を感じました。以前は新社会人として共感できたのに。
難しい言葉が頻繁に登場し、物語にもついていけるか不安になりましたが、後藤の怒声で我に返り、再び仲間たちが集まる姿に胸が熱くなりました!やはり泉と遊馬が活躍するシーンがあると嬉しいですね。今回の作品がより現実的なのは理解していますが。
大傑作だ。ひとつの事件がきっかけで取り返しのつかない事態へと転がり、戦争が勃発するまでを圧倒的なリアリティで描くため、視聴者は自然と戦争の当事者として立ち現れる。こうした観客の巻き込み方は庵野秀明の系譜を感じさせ、もしかすると「まごころを君に」がその流れを受け継いで生まれたのではないかと推測させる。柘植がPKOに派遣されたとき、9条のせいで発砲を躊躇し部下が死んだことが動機だとされるが、そもそもPKO派遣自体を違憲だと私は考えている。しかし、そうした諸々を有耶無耶にしたまま日本という国はここまで来た。柘植は今一度考え直そうと語るのだ。ということは、この映画を語るとき私たちは戦争の当事者となり、自分の政治的立場を明らかにして語らねばならないということだ。ウクライナ戦争が始まったとき、日本に改憲ムードが広がったのを見て私は護憲の立場に転じた。他国が戦争を始めたとき、一度捨てた銃を拾い直すべきだと考えれば、結局はそのうち戦争へと向かうのだと。長い間、愛国心というものを理解しきれなかったが、三島由紀夫と東大全共闘を見返したときに少し理解が深まった。日本への愛着阿佐ヶ谷のこの風景が変わってほしくないという思いそれが私の胸にある。パトレイバー1は、そうした愛国心を問いかける側面を持つのではないか、という見方もできる。9条は押し付けられた憲法だという意見もあるが、仮にそうであっても私はこの憲法を持つ日本に生まれ、23年を生きてきた。だからこそ憲法への愛着が生まれ、世界最高の平和憲法を持つ国に生まれたことを誇りに思う。9条をこれまで一切変えず守り続けてきた日本が好きだ。私は9条を日本の象徴だと信じている。そんな愛国心を抱えつつ、世界は今、戦争へと急速に向かおうとしていると感じる。だからこそ「遅すぎた」と言わせないための対話が必要だ。映画の中で対話を交わしたのは後藤と荒川だけで、警察の上層部は沈黙している。民主主義は今や多数決の論理になりがちだが、本当に大切なのはみんなで考えることだ。右と左も対話しなければならない。資本主義社会そのものを批判する一貫した視点を通じて、この作品は私たちに戦争を考えさせ、自らの意見を表明する力を引き出そうとしている。テロリズムではなく映像表現でそれを成し遂げた押井守監督に、最大限の賛辞を贈りたい。
パトレイバー1に続いて視聴しました。
東京の街で展開される「架空の戦争」を描いた作品です。
まず断言したいのは、本作は前作とは別物として捉えるべきで、パトレイバー感はかなり薄いです。1に比べると、大衆娯楽性は控えめで、画表現を含めてテーマ性が強く打ち出された作品となっています。監督が「論文のような作品」と表現したことが、本当に的を射た言葉です。
動きは少ないものの、優れた画表現や人間描写は多くの場面で感じられ、圧倒されました。テーマとしては、本作は1で描かれた「未来」から一歩離れ、脆弱な土台の上に成り立つ現在の日常への問題提起を行っています。作風は異なるものの、1のテーマと繋がる内容です。
この背景には、1989年の1作目公開時には景気が良く未来への希望があったのに対し、1993年に公開された2作目はバブル崩壊と湾岸戦争直後という不安定な時代背景があります。このように、戦争の不安が続く中で「何かが起こりそうな」雰囲気を、本作は全ての技術を駆使して見事に表現しています。
こう考えると、押井監督の作品は一見難解に思えながらも、その時代性を非常にわかりやすく描いていると思います。
本作のシナリオ上の魅力は、後藤隊長にあります。前作からその片鱗を見せていた彼は、非常に魅力的で、見かけは「良い上司」に思えるものの、本質的には非常に狡猾なキャラクターです。国家のしがらみを巧みにかわし、部下を動かす姿は、人が「悪い人」に引かれる理由を考えさせられるもので、今度からは本作を紹介したいと思いました。後藤隊長を含む、底知れぬキャラクターたちは、やはり押井パトレイバーの魅力の一部でしょう。
この作品は、ただのアニメ映画に収められるものではなく、未来を展望する上で参考にしたい名作でした。何度も見直すほどに深みが増す作品だと感じています。
後半の反撃や有視界戦闘は良かった一方、前半の攻められている描写が分かりづらすぎる。
『この街は、現実の戦争には狭すぎる。』
中学生から高校生、さらには大学生や20代の頃まで、押井守監督の作品に触れた瞬間、誰もが魅了され、ついていく覚悟を決めてしまうそんな特別な力を持つ監督の作品群の中でも、本作と出会えば、もう後戻りはできない。飽きることのない日常を潤してくれる、強い成分が満ちている。
不正義の平和と正義の戦争。今も続く戦いをテレビの中に押しこみ、日々の暮らしを虚無で満たしてしまう世界。そんな穏やかな日常に、突然のミサイル、国内は混乱へと翻弄される。そんな局面で描かれる男と女の物語は、観る者の心を掴んで離さない。愛と戦い。非日常と非現実、妄想に満ちた世界が、この映画には閉じ込められている。誰かが言った。「偽物の方が、本物よりも本物だ」と。
柘植行人押井守作品に度々登場する演出家として、すべてを破壊してきた彼が、最後に残す言葉。その言葉を前に、僕らはいつも気づかされる。確かに、日常は空虚かもしれない。誰かの血の上に成り立っているのかもしれない。でも、それでも生きたい。未来を見たい。だから疼くのだ。見たい未来を、しかし見えない。だからこそ、日々は長く感じる。その不安と戦うために、きっと僕らは映画を観る。
準備はできている。再び、日常と戦おう。自分の見方次第で、日常は想像以上に輝くはずだ。何度もそんな気持ちで戻ってくる。非日常と非現実を求めてしまうとしても、それでいい。現実の世界の戦いは僕には過酷すぎる。時には羽を休め、再出発のために何度でも観る。噛みつき、飲み込み、そして日常へ戻る。
どこまでも惹き込まれる会話と、衝撃的な展開。究極のポリティカル・サスペンス。僕を揺さぶり、潤してくれる押井さん。これから先も、どうぞよろしくお願いします。
現代文明の高度な発展は、多大な犠牲の上に成り立っているという自明の真理がある。しかし、そこから目を背けようとする現代人に対して、柘植は警鐘を鳴らしたのではないか。犠牲とは、すなわち戦争の代償である。戦争の記憶を忘れてしまったり記憶を欠く人々に、改めてそれを思い起こさせようとしたのだろう。いずれにせよ、二・二六事件のように東京に戒厳令が敷かれる緊迫した情景は、見る者に強い緊張感を与え、興味を引く。1800円の価値は十二分にあるはずだ。
平和に夢中な人々への警告として発射されたミサイル1発は、現代ではTwitterの噂話数件で済んでしまうかもしれません。
以前1を映画館で観て圧倒的に面白かっただけに、続編となる2を観るのをとても楽しみにしていました。前作と比べると、今作は難解さが増し、いわば大人向けの深みを感じる作品です。1はとにかく動く!といったミステリースリラー路線でしたが、2はクールでシリアスなトーンへと展開が変わった印象です。序盤は1のような展開を想像していたものの、すぐに強いシリアリティが立ち上り、見た目は似ていても毛色が違うと感じました。前作を観ている身として、後藤さんと南雲さんに焦点を当てた作りが新鮮で面白かったです。個人的には1のパトレイバーらしさがやはり好きですが、2は押田守の存在感が全面に出ていて、それもまた良いと感じました。とりあえず、アクションよりセリフの方が重視されている点が印象的でした。
主役コンビの活躍を期待していたのに、登場したのは年配のキャラクターばかりだった。自分の趣味に走るのなら、既存のコンテンツに頼らず、完全オリジナルを一から作るべきだと感じた。
リバイバル上映を観てきました。
当時は映画館に行く余裕がなかったので、100円レンタルビデオのタイミングで借りて楽しんでいました。
今見ると解像度も向上しており、非常にクオリティの高い映画だと感じました。
魚眼レンズを用いた映像が多く見られ、リアルなキャラクター表現にしか映えないと感じました。二次元キャラクターの平面的な顔ではうまく機能していないように思います。それはさておき、この作品はかなりオタク寄りですね。
PKO(ピースキーピングオペレーション)を背景に、東南アジアの紛争地域へ派遣された自衛隊のレイバー小隊がゲリラと遭遇、攻撃を受けるも発砲許可が下りず壊滅。唯一生存したのは小隊長の柘植行人であった。
特車二課第2小隊は隊長・後藤と山崎を別々の場所で任務に就かせ、それぞれの仕事を進めている。課長代理に昇進した南雲は会議の帰路、渋滞にはまる。自動車に爆弾を仕掛けたとの犯行予告を受け警察が対応する中、戦闘機から一発のミサイルが発射され、橋が爆破される。
戦闘機が自衛隊機と報じられる一方、のちに荒川と名乗る男が後藤と南雲を訪ねてくる。荒川の話では、あの戦闘機は米軍所属で、橋を爆破させるよう仕向けた黒幕がいるという。その名は柘植行人。南雲のかつての指導者であり、かつての恋人でもあった。
人物の描写が印象的な点が光る。今作では人物が大きく動く場面は少なく、構図を決めて会話を重ねる場面が多い。画面の中で座ったり立ったりする佇まいに説得力があり、構図・背景・設定・撮影といった総合力が作品全体を支える。風景の中に佇む人々を観客は見ることになる。
もちろん、冒頭の銃撃・破壊・爆破といったダイナミックな場面もある。静と動の対比がこの作品の独特の魅力を築いている。
ユーモラスな場面も適度に配置されている。荒川が持ち込むVHSの内容とそれに絡むやり取り、進士夫妻が演じる愁嘆場には、意外にも笑いが起きる。作品のトーンを損なわない程度の適度な可笑しさの加減も心地よい。
さらに、ばらばらだった小隊が終盤で再結集する展開は熱い。読書のようにじわじわと高まる緊張感と連帯感が同時に走る瞬間が見どころだ。
本作は1992年にPKO法が制定され、1993年の公開時には自衛隊が海外へ展開する法的根拠が現実のものとして動き出していた。時代のタイムリーさを反映した題材である一方で、それだけが本作の核ではない。憲法9条下の戦力不保持を掲げる日本における自衛隊の存在とその矛盾を端的に描く要素が物語の軸にある。作中では戦地で発砲許可が出ず自衛すら難しい自衛隊の実情を描き、法の解釈と現実のギャップを浮き彫りにする。それが本作の主題のひとつとなっている。
もうひとつの主題は戦後の発展を支えた戦争特需の不可欠性と、それに伴う欺瞞の構造だ。戦後の経済成長は局所的な巨大な消費と需要を生み出し、それが国際通貨を獲得する道を開いた。しかしその背後には不正義の平和を保つ仕組みが潜むという見方もできる。こうした矛盾と欺瞞こそが本作の核にあると考えられる。
日常の風景の中に戦車や武装レイバーが配される画面こそが、この作品の核を支える要素だ。矛盾は自衛隊として、欺瞞は都市生活の風景として描かれ、ショーウィンドウに隊員が反射する場面は、欺瞞が進んだ先の消費社会を映し出しているように感じられる。
本作と前作を通じて、戦後日本の経済成長の陰の部分を描き出している。開発の急速さが原風景を奪い、成長の背後には他国の戦争によって生まれた恩恵が潜んでいるという見方も成り得る。こうした不正義の平和を、自衛隊と警察がどう受け止め、どう進むべきかを問う構造が印象深い。
何度観ても、やはりこの映画は良作だ。前作と同様に繰り返し観賞したくなる魅力を備えている。
原作ヘッドギア、脚本 伊藤和典、キャラクターデザイン 高田明美・ゆうきまさみ、メカニックデザイン 出渕裕・河森正治・カトキハジメ、監督は押井守。1993年 日本製作。日本についての映画。