2025年6月13日に公開の映画「フロントライン」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「フロントライン」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
フロントラインが視聴できる動画配信サービス
現在「フロントライン」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「フロントライン」が配信中です。
フロントラインのあらすじ
2020年2月、乗客乗員3,700名を乗せた豪華客船が横浜港に到着した。香港で下船した乗客の一人に新型コロナウイルスの感染が確認され、この船内でも感染が広がり、100人以上の乗客が症状を訴える事態となっていた。
こうした状況に対処するために出動したのは、災害派遣医療チーム「DMAT(ディーマット)」である。彼らは地震や洪水などの災害に対応する専門家だが、未知のウイルスに対処するための経験や訓練は受けていなかった。…
フロントラインの詳細情報
「フロントライン」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
フロントラインの公式PVや予告編動画
「フロントライン」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
フロントラインの楽曲
「フロントライン」の主題歌や挿入歌、サウンドトラックを紹介します。映像だけでなく音楽からも作品の世界を感じてみましょう。
- サウンドトラックフロントライン (Original Soundtrack)Steven Argila
フロントラインを見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
フロントラインを無料で見る方法は?
「フロントライン」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
フロントラインのよくある質問
-
Q映画『フロントライン』のあらすじはどのような内容ですか?
-
A
映画『フロントライン』は、朝鮮戦争中の物語で、終戦間際の前線で繰り広げられる戦闘や兵士たちの葛藤を描きます。敵味方の狭間で友情や人間性が試される様を深く探る内容です。
-
Q映画『フロントライン』の主要キャストには誰がいますか?
-
A
映画『フロントライン』の主要キャストには、シン・ハギュン、コ・ス、イ・ジェフンなどがいます。彼らの演技が人間ドラマを深く表現しています。
-
Q映画『フロントライン』のテーマは何ですか?
-
A
映画『フロントライン』のテーマは、戦争がもたらす悲劇と、それに立ち向かう人々の勇気と絶望です。戦場での人間関係の複雑さや、個人の選択がもたらす影響を描いています。
-
Q映画『フロントライン』の制作背景にはどのようなエピソードがありますか?
-
A
映画『フロントライン』は、歴史的な事実を基にしており、リアルさを追求して制作されました。撮影は主に韓国で行われ、緻密なセットと特撮によって戦場の臨場感が再現されています。
-
Q映画『フロントライン』は観客からどのように評価されていますか?
-
A
映画『フロントライン』は、そのリアリティのある描写と深い人間ドラマが評価されています。観客は、戦争を通じて考えさせられるメッセージ性に強い感銘を受けています。
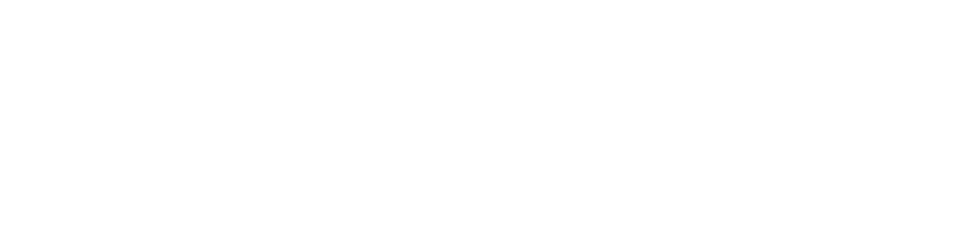




フロントラインの感想・評価
過度にドラマチックにする必要はない。NHKの社会派2時間ドラマのような落ち着いた雰囲気。
ドラマ性を強く出さず、自然体で。NHKの社会派2時間ドラマのような感触。
派手さを抑え、リアル寄りに。NHKの社会派2時間ドラマのような、静かな緊張感を持つ雰囲気。
現場は厳しかったし、その頃はみんなが批判に回っていたね。六合医師のYouTube動画を観たけれど、特におかしなことは言っていないように感じた。
特別な出来事があるわけではないけれど、コロナの初期に尽力した医療従事者たちには頭が下がる思いだ。当時は自分にとって遠い世界の出来事のようにニュースを見ており、知らず知らずのうちにメディアに影響されて差別的な感情を抱いていたかもしれないと反省している。何事も、裏側には多くの人々の努力と葛藤があることを忘れてはいけないと思う。
DMATの果敢な姿を映し出す映像。
現場での迅速な対応と献身をリアルに伝える、力強いドキュメンタリーです。
事実に基づいているとしても、状況は非常に厳しく、皆が自分のことより他者を優先することに苦労していたのではないでしょうか。
職業上「人に尽くす」ということが最優先になると、このような状況では辛さが増しますね。
当時を思い返して映像を見ていたら、自分の知らない場所でこんなにも頑張っていた人たちがいるのだと深く感銘を受けた。人のために尽くしているのに、世間からは汚名のように扱われて胸が苦しくなった。窪塚洋介が机を叩くシーンの気迫は圧巻だった。
コロナ禍の物語。未知の状況やリスクを抱えながらも、人道的な視点を持つことがどれほど重要か、自分自身に問いかける経験をした。そして、マスメディアが報じる内容が必ずしも真実であるとは限らないということについても考えさせられた。
この映画を観て本当に良かった。DMATの方々やダイヤモンドプリンセス号のクルーの皆さんへ、心から敬意を表します。人道的に正しいと思って行動する力の重さが、胸に刺さる言葉『人道的に正しいと思ったから』に凝縮されていました。信念のもとに動ける人は本当に強く、尊敬します。松坂桃李さんが演じた立松の、冷たい口調の中に滲む優しさを描く演技がとても印象的でした。️
小栗旬と窪塚洋介の絡みが、胸を打つほどエモい。ディーマットという存在を、この映画で初めて知りました。医師・官僚・プリンセスダイヤモンドのクルーたちは、それぞれの立場で果たすべきことを優先し、目の前の命を救うことを最優先に動いていたのだと、やっとあの時の真実を知ることができました。当時は私自身もマスコミの印象操作にまんまと操られていたと、今振り返って気づきます。実際には13名が亡くなったとWikiで知りましたが、映画ではその部分は描かれていませんでした。長い間バックで流れる感動的な音楽と、滝藤さんの演技、そして外国の兄弟2人の場面には、私も涙しました。
やれることはすべてやり抜く!私も医療従事者として胸を打たれました。船内の様子や職種ごとの葛藤が、見事に描かれていました。
事実を軸に据えた物語として、無理にヒューマンドラマへ寄せて涙を狙う作りではなく、そんな配慮が好印象だった。
ただ、意外性の薄い配役や、官僚と現場の描き方にはいつものヒーロー映画的な要素が散見され、現実味への没入はやや阻まれた。現実と地続きの感覚を重視するなら、TBS系のドラマのほうが鑑賞後の余韻が深いと感じる。
マスコミの愚かさを揶揄する場面もあるが、その雑な描写は「オールドメディアを揶揄する程度の軽さ」と言わざるを得ず、映画としては物足りなく映ってしまう。終盤の桜井ユキさんと小栗旬さんのやり取りは、道徳的結末に着地してしまった印象が残る。全体としてポスターの印象と一致していた。
大勢の観客を動員することと専門性の高さは両立すべきだが、現状は前者を優先した作りと映り、やや説得力を欠く場面があった。エンドロールでのマスクの言い訳めいた台詞も、受け取り方がふわっとしてしまう。
それでも、森七菜さんと池松壮亮さんが登場する場面には強く引き込まれた。
コロナが終息し、マスクを外したとき、普段の生活がどれほど貴重だったかを実感しました。その瞬間を振り返ると、今はその感覚が薄れてしまった気がします。医療従事者を支援するビジネスに関わることができれば嬉しいです。デジタルトランスフォーメーションによって命を救えるなら、自分にその適性があるのか不安もありますが、自信が持てない中でも、今後はこの分野で自分の価値を発揮できるポジションを探していきたいと思います。
就活生より。
U-NEXTで視聴しました。
当時のことを思い出して、なんとなく見てみました。最前線で頑張っていた多くのスタッフのことを考えると、胸が痛みます。当時、私が働いていた病棟で発生したコロナクラスターのことを思い出し、辛さや燃え尽きていた気持ちが蘇りました。N95の跡が残り、肌が荒れていたことさえも懐かしく感じました。
観てよかったと思いますし、ぜひみんなにも観てほしいです。
さておき、シンプルに仕事のドラマがつらくなってしまった 組織運営の厄介な問題100選
ダイヤモンドプリンセス号に関わった医療従事者、テレビ局、乗客、クルーのストーリーについて。映画も素晴らしいけれど、テレビで取り上げられることで多くの人に知ってもらいたいと思った。医者や看護師であっても、未知の危険なウイルスが広がる環境に立ち向かうその勇気と使命感には心から敬意を表する。何も知らない人々が批判をすることで、当人やその家族が苦しむのは本当に残念なことだ。だからこそ、メディアには正確な情報を伝えてほしい。また、偶然その場で働いていたクルーたちが自分の役割を果たしている姿も、医療従事者と同様に尊敬に値する。もし自分が同じ立場にいたら、非常に不安だっただろうし、逃げ出したくなるのも理解できる。
人の素晴らしさを改めて実感できる映画だと感じた。
派手な展開はないのに、2時間強の長さがあっという間に過ぎる。
社会的テーマを扱う作品には偏りがあるかもしれないと敬遠してきたが、この作品はその先入観を感じさせず、中立的で丁寧に人間を描き出し、私は強く共感した。
もう5年も前、いや、まだ5年か。世界中が先の見えない不安に包まれたあの頃。今もコロナが出た流行ってるといった話題は耳にするけれど、会話のトーンはあの頃とは違う。あのときは、得体の知れないウイルスが社会を揺さぶり、店からマスクが消え、外出も減り、会話も減っていった。
普段は菌が蔓延する病院でさえ、コロナのせいで働けないと感じるそんな声もあるし、小栗旬の気持ちも分かる。医療従事者の気持ちも理解できる。ただ、やっぱり怖い。
反論すべきか。反論しても、都合のいいところだけ切り取って放送され、意見が寄せられ、反論へと時間が費やされる。マスコミとは。コロナを通じて、テレビ業界やマスメディア、新聞を含む情報の真偽を考えるきっかけになった。
お兄ちゃんが死んでもいいから弟の側にいたい。そして、最後の前田亜希ちゃんの演技にもう涙腺が崩壊。
からの、先日から始まった『ヒポクラテスの盲点』。上映されている映画館は少ないけれど、観に行きたいな。
コロナ時代を思い出しながら視聴した。目に見えないものの恐ろしさを改めて感じた。ニュースでしか知らなかった事実を、見えなかった部分まで知ることができた。
『そこにアンパンマンがいました。自分を強くする映画』は、全国民が一度は観るべき作品として強く推したい映画です。観ればスコア以上の価値を感じられるはずです。
新型コロナウイルスに関するパンデミックは、これからも多くの映画やドラマの題材になるでしょう。自分たちの死後も後世に伝えるべき災害として、私たちはどう向き合うべきかを問います。
この映画は、時代の変化に耐えうる普遍的なテーマを持っています。ダイアモンドプリンセス号で実際に起きた出来事を基に、未知のウイルスに最前線で立ち向かった医師や看護師たちの闘いを描く。国内感染拡大を防ぐべき公的方針と、乗客の人命を最優先にする医療現場の判断の間での葛藤が克明に描かれます。
『自分の仕事じゃないから』『ルールがないから』といった視点ではなく、アンパンマンのような『揺るぎない正義』を持ってどう行動すべきかを、私たちはこの作品から学ぶべきです。さらに、マスメディアによる過剰な大衆煽動にも警鐘を鳴らします。災害だけでなく、不幸を笑う人々や勇気ある人々に対する偏見にも、強い怒りが湧き上がります。
恥ずかしいことに、私はこの作品を観るまで、船内の重症患者の家族や陽性者の子どもだけが船内で孤立させられる状況、献身的に看護する医師・看護師の家族への誹謗中傷など、現実の痛みに思いを至らせていませんでした。乗客と全体方針の板挟みになるクルーの苦悩も同様です。コロナ福そのものより、そこに潜むメンタルの負荷が深く心を蝕んでいくのです。
3.11、広島、長崎、沖縄、そして世界で起きている戦争や社会問題は、いまも私たちに身近です。情報の取捨選択を自分の責任として行い、そこから自分の行動を起こす。医師でも政治家でも軍人でもない私たちだからこそ、正しい行いをしている人々の妨げにならないよう、日々の行動を意識したい。
この映画を機に、私たちも『強く・優しく・正しく生きる』ための選択をしていきましょう。
実話を基づく作品だが、人物の活動を一人にまとめる脚色も指摘される。それにもかかわらず、事実の迫力は十分に伝わってくる。NHKのプロジェクトXがダイアモンドプリンセス号でのDMATの活躍と苦悩を描いたことと同様、本作もDMATの視点に留まらず、厚労省、マスコミ、乗客・乗組員、受け入れ先病院といったさまざまな視点を重ね合わせることで、感染事故の全体像を明確に示している。人間ドラマとしての感動も深い。しかし民放とされるテレビ局の報道姿勢には不満を禁じ得ない場面が多く、実話であればなおさら残念だ。とはいえ、未曾有の危機に命を懸けて闘ったDMATをはじめとする人々には頭が下がる。映画はそうした努力と意義を伝え、記録として残す価値を改めて感じさせてくれる。