2025年2月21日に公開の映画「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないが視聴できる動画配信サービス
現在「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」が配信中です。
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないのあらすじ
ヨルダン川西岸地区のマサーフェル・ヤッタで育ったパレスチナ人青年バーセルは、イスラエル軍の占領が進む中、故郷の村が破壊される様子を幼少期からカメラで記録し、世界に発信していた。そんな彼のもとに、イスラエル人ジャーナリストのユヴァルが訪れる。彼は自国の非人道的で暴力的な行為に心を痛め、バーセルを支援しようと危険を顧みずこの村にやってきたのである。共通の思いを抱えるうちに、互いの境遇や気持ちを語り合い、同い年の二人の間に予想外の友情が芽生えていく。しかしその一方で、軍の破壊活動は過激化し、彼らがカメラで捉える映像には、徐々に痛ましい犠牲者の姿が増えていくことになる。
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないの詳細情報
「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 監督 | ハムダーン・バラール バーセル・アドラー ユヴァル・アブラハーム ラヘル・ショール |
|---|---|
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | ドキュメンタリー |
| 制作国 | パレスチナ ノルウェー |
| 公開日 | 2025年2月21日 |
| 上映時間 | 95分 |
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないの公式PVや予告編動画
「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないを見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないを無料で見る方法は?
「ノー・アザー・ランド 故郷は他にない」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないのよくある質問
-
Q映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』のあらすじはどのようなものですか?
-
A
『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』は、故郷を離れた主人公が、自分の起源やアイデンティティを再発見する物語です。彼の旅と人々との出会いを通じて、家族の絆や文化的な背景が深く描かれています。
-
Q『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の主要キャラクターは誰ですか?
-
A
この映画の主人公は故郷を離れた青年で、彼の成長を軸にストーリーが展開されます。その他、彼を支える家族や新たに出会う友人たちも魅力的に描かれています。
-
Q『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』のテーマやメッセージは何ですか?
-
A
この映画は故郷や文化の重要性を探求し、アイデンティティの形成や家族の絆を強調しています。どこにいても自分のルーツを大切にすることの意義を描いています。
-
Q『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の制作に関わったスタッフや監督について教えてください。
-
A
『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の監督は、情熱的に人間の感情や文化を描くことで知られています。この映画でも彼らの独自のアプローチが随所に見られます。
-
Q映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の評価や人気の理由は何ですか?
-
A
『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』は、故郷やアイデンティティに対する深い洞察と共感を呼ぶストーリーで、多くの観客から高い評価を受けています。感情豊かでリアルな人物描写が、共感を呼んでいます。






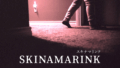
ノー・アザー・ランド 故郷は他にないの感想・評価
家が長く崩される光景が続く。幼い頃から住んだ家を離れると、がらんとした家を見て涙がこぼれた。その感情は、何倍にも濃くなった絶望へと変わっていく。
なぜこんなにも人々は耐えられるのか。軍に対して諦めてしまうのか。理不尽に対しても、彼らは正々堂々と抗議している。家も財産も命も、奪われるばかりだ。
自分には偏見がある。見ていると、ただ無力化された人々に過ぎないようにも見える。いつか自分たちが追放される日が来ると、どこかで悟っているのではないかという疑い。だが、それは醜い偏見だ。機能する国でこそ、そんな平和ボケした言説は成立しづらいのかもしれない。
こんな理不尽な目に遭い続ける理由を考えずにはいられない。正常性バイアスに近い感覚だ。調べてみれば、それは公正世界仮説と呼ばれるものらしい。善い人には善いことが、悪い人には悪いことが起こると信じたいがゆえに、被害者側にも何か非があるはずだと理由を探してしまう心理だ。
だが実際には、彼らは犯罪者でも不法占拠者でも武装勢力でもない。ただ社会的に弱い立場にいるだけで、世界から見捨てられないために正当な抗議しか選べない状況だ。投票権もない。
法律は、彼らを追い出すことを都合よく正当化しているように感じる。イスラエルの法は、違法建築や違法な井戸といった事例を挙げつつ、後から来たのはイスラエルからの入植者だろうと指摘されることもある。
イスラエル人はパレスチナ人をあえてアラブ人と呼ぶことがある。パレスチナ人と呼ぶと、彼らの土地に根ざす文化や国民としての存在を認めることになるからだという。広い地域のどこにでも住めるアラブ人と呼ぶ方が都合がいいらしい。
シオニストは今やレイシストと並ぶ不名誉な語として扱われるべきだと感じる。アパルトヘイトにも勝るとも劣らない人権侵害が、いまこの地で続いているのだ。
最初はアメリカが助けてくれると信じていたのだろう。映画を観たいと思ったときには、もうどこでも見られない状況だった。しかし今、U-NEXTで視聴できると知って、嬉しく思う。
ガザではなく、ヨルダン川西岸地区でのイスラエルの入植者や軍の行動を記録したドキュメンタリー。
なぜパレスチナ人が入植者によって命を奪われても、日本ではあまり報じられないのだろうか?
他国で発生する銃乱射事件とは何が違うのだろう?
ガザも西岸地区も、それぞれ異なる苦しみを抱えていると感じるが、そこに暮らす人々は非常に強い。
しかし、この状況を無視し続けることは許されるはずがない。
どうしてそんなことができるのだろう。
つい最近まで人々が暮らしていた建物や小学校が壊され、井戸にコンクリートが流し込まれ、地域の人々の生活が一方的に奪われていく様子を見ているのが本当に辛い。
何とかならないものか本当に。
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞した作品です。パレスチナの村マサーフェル・ヤッタが、イスラエル軍によって壊されていく過程を、パレスチナ人とイスラエル人の二つの視点から描き出します。印象的なのは、単一の被害者視点に偏らない構成。アラブ人のバーゼルと、ユダヤ人ジャーナリストのユヴァルは、背景も立場も異なる二人ですが、同じ崩壊を見つめながらも現実の受け止め方は温度感を伴って微妙に異なります。ユヴァルは、少数派左派という立場から状況は変えられると信じ続け、そこに希望を感じさせます。一方、バーゼルの語りは終始現実的で悲観的。家が壊され、生きる場所が奪われ続ける現実の中で、未来を信じる余裕が徐々に薄れていきます。
二人の交流には、国境や宗教を超えた連帯の予感もありますが、決して本質的に分かり合えるわけではありません。国家と無権利、占領する側とされる側という非対称性が、二人の間に越えがたい壁として立ちはだかるのです。それでも、同じ場所に立ち、破壊を記録し続ける行為そのものが、かすかな希望として光を灯します。イスラエル・パレスチナの問題は、世界がもっと深く知るべきテーマだと強く感じさせる作品です。
マサーフェル・ヤッタの占領を追うドキュメンタリー。イスラエル軍による小学校の破壊シーンは特に衝撃的だった。イスラエル軍の視点にも焦点を当てた構成を望む。
「マザーフェル・ヤッタ」地区で、イスラエル軍の武力行使が平然と続く。話が通じない相手にどう対抗すればよいのか。嫌がらせと破壊行為が日常を蝕む、地獄の日々の記録だ。
小学校が破壊され、子どもたちへ暴力が向けられる場面は耐え難く、こんな理不尽の連鎖の中で正常な判断を保てるのかと胸が痛んだ。
虐げられていた者が、今度は虐げる側へ回る最悪のスパイラル。「現在の彼らには強力な軍と高度な技術がある。しかし、弱かった時のことを忘れるべきではない」。
向き合うのはつらいが、観てよかったと感じる作品だった。
言葉を失うほどの衝撃で、感想すら言い出せなかった。遠い昔の話ではなく、今もなお続いている現実を、これまでなんとなく見て見ぬふりしてきただけだったと気づかされる。これを目の当たりにしてしまい、スタバもマックも、もう行きたいと思えなくなってしまった。
不条理に対する怒りと虚しさが心を痛める。21世紀になった今なお、恐怖を克服するために非人道的な行為が平然と行われている現実が存在する。同じ過ちを繰り返さないように学ぶべきだと思うが、それでも世界中の人々がこの事実を知ることは重要だ。
家屋の破壊は最悪で、発電機を盗もうとしたり井戸を埋めたりする行為はそれ以上に悪質です。ジャーナリストとの交流がある点は評価できます。命の危険が伴う状況でも情報を公開しているのだから、ぜひ視聴すべきです。
危険を冒してでも記録し伝えようとする製作者たちには、ただ敬意を感じる。多くの人に知ってほしい現実が、そこには確かに描かれている。
明らかに国際法違反とされるイスラエル軍・入植者の暴力、人権侵害。さらにそれに抵抗し続けるパレスチナの人々と、立場を超えた協働。これらを知ると同時に、構造的・政治的な残酷さを痛感させられる。敵味方を超えた命がけの友情の宣伝的なまとめ方には違和感を覚えるが、宣伝は難しいことも理解できる。
主にバーセルとユヴァルの二人を中心とし、ナレーションは少なく、目の前の事実を淡々と映す作り。背景説明は多くなく、ある程度の前提知識が求められる。現在ではガザ地区の報道は増えつつあるが、西岸地区はまだ十分とは言えないと感じる。
以前観て良いと思ったのは、2013年に公開されたYouTube版のドキュメンタリー(リンクあり)。いかにパレスチナの人々がカメラを持つことで抵抗していくかを描く一方、入植者側のインタビューや歴史など背景説明もある。興味があれば併せて観るとよいだろう。
以下は印象に残った箇所のメモ
︎「もう帰るのか」と何度も問われるユヴァル。志は高いが、社会構造の差が埋められないことの象徴。パレスチナ人にとっては常にno other landの状況でも、ユヴァルには帰る場所がある。
︎トニー・ブレアが視察した学校と家々の破壊は止まる。英国の介入は一時的な効果をもたらすが、国際社会はイスラエルの暴挙を完全には止められない。政治の残酷さ。
︎言語
・日本語字幕ではアラビア語と英語が括弧なし、ヘブライ語が括弧付き。言語が本作の重要な要素であることを示しており、字幕の工夫は良かった。
・ユヴァルはアラビア語を学んだことで価値観が変わり、諜報員の勧誘を断つ。村人の詰問にも暴力ではなく対話で応じる。言葉と文化を学び活かすことの意味。
・バーセルは英語もヘブライ語も話す。兵士に訴えるときはヘブライ語、兵士はヘブライ語のみという場面も。通訳的な兵士がいるはずだが、力の関係性を感じる瞬間もある。バーセルは弁護士の資格を持つほど優秀だが、パレスチナ人であるがゆえにその力を存分に発揮できない。
・ジンバ村から来た車。給油後も開いたままの給油フタに見えたヘブライ文字。意味深に映るが、後で黄ナンバーを示す入植者サインではないかと想像してしまう。
・街の標識にはアラビア語とヘブライ語が併記されている。
この映画は虐殺を警鐘として機能しきれなかった。不当に不条理に家が壊される記録映像は、虐殺の前日譚にほかならない。イスラエル兵は話の通じない何かへと変貌しており、人間としてのぬくもりを失っているようだ。一方で、イスラエル人ジャーナリストのユヴァルは出自を超え、パレスチナの人々に同情する。国境という目に見えない境界が人々の絆を断ち切るわけではなく、むしろ国家が障害となる場面のほうが多い。ジャーナリストと現地の人々の軋轢は、国家の枠を超えた普遍的な現象として浮かび上がるように感じられる。さらに、国家の名の下で国境を意識し、身につけるものさえ国家に属するようになると、個人の意思は見えなくなる不気味さが生まれる。平然と発砲が続く映像は、観る者の胸を深く痛ませる。
これはまだ前日譚にすぎず、私たちが今目にする現実の虐殺へと歩み始めるのだろうかと、心が痛くなる。「Black Box Diaries」にも通じる、個人の無力さと国家の横暴さ、権力の無責任さが、耐え難いほどの重さとして迫ってくる。
しかし、つい先日イスラエルは停戦に至り、パレスチナにはいっときの平和が訪れた。束の間の平和は長続きするかは未知であり、これまでの冷酷非道ぶりを考えると確証は得難い。パレスチナ国家を認めた諸外国でさえイスラエルへの具体的措置にはまだ腰が引けている。日本は国家としての承認すら揺れており(石破茂が総理大臣であってもアメリカに歯向かえるとは限らない現実もある)。酒の席で仕事の建前と本音を語る機会は多いが、本音の部分が腐っていると感じる場面は少なくない。国と国との関係にも、そんな本音の腐敗が潜んでいるのだろうか。どうすればこの矛盾を飲み込み、前へ進めるのか。
闇夜を照らすサイレンの光、カーキ色の武装兵士、ぶれるハンディカメラの映像、乾燥した大気の中で、子どもたちの笑顔と叫び声が響く。活動家の両親のもとに生まれたアディールは、不屈の精神を持つ少年だ。父は何度も警察に逮捕されながらも活動を続け、村の土地がイスラエル軍の軍用地となる中で、住民たちは暗く不衛生な洞穴へと避難せざるを得なくなる。ユダヤ人のユヴァルは、アディールのいる地域に近づくと、集まった人々は嘆きの声を上げる。父親はユダヤ人への憎しみを抑え込んでおり、アディールはその怒りの中で自我を失いかけている。故郷を追われようとするアディールと、帰る家があるユヴァルの対比が際立つ。立ち退きや「違法建築」の破壊が進む中、目の前で家が壊され、子どもたちが狙われる恐怖が広がる。大工道具さえ奪われ、生命線となる発電機も狙われる中で、抵抗したハーマーンが撃たれる。
ハーマーンが四肢を失ったことを受け、小規模な平和的デモが行われるが、イスラエル軍は常に監視している。アディールは、「バラバラになると手榴弾で狙われる」と警告するが、冗談のように思っていた事が現実となり、実際に手榴弾が炸裂して阻止される。子どもたちがデモを続ける中で、週3回の抗議が少しずつ村への破壊活動を抑制する希望となる。しかし、アディールは「イスラエル兵に逮捕されるかもしれない」との脅しに直面し、ストレスと戦うことになる。
どんな朝でも、子どもたちは学校へ向かい、父に頼んで送り届けてもらう。女性と子どもたちは日中に働き、男性たちは夜にひっそりと稼ぎ、やっとの思いで設立した学校が希望だった。教育が未来の道を拓くと信じていたのに、アディールは法学の学士を持ちながらも、弁護士として働くことを選ばない。経済の破綻したパレスチナでの職は見つからず、再び父が逮捕され、家族を養うため活動を一時的に辞めてガソリンの販売を始める。
ブルドーザーが別の村へ向かう中、ユヴァルだけがそれに乗る決心をする。アディールはその決断に迷いながらも、結局は行かないことを選ぶ。ユヴァルは、抗議を続けるが、入植者たちに動画を撮られてしまう。カメラは社会に向けた銃口のように感じられ、彼らもまたドキュメンタリーとしてその瞬間を捉えている。カメラが武器となる現実を目の当たりにし、イスラエル軍は、マサー・フェルヤッタの人々の声に無慈悲に耳を傾けることなく破壊を続ける。
催涙弾が投げられ、ユダヤ人の車とパレスチナ人の車が対比される中、パレスチナの地で家族を持つことの重みと不安定さが際立つ。ユヴァルもタバコを吸い始め、追放が始まる。許可証も司令書もない状況の中、家が壊され、マサー・フェルヤッタは人の住めない土地へと変わっていく。隣接する住宅街から、入植者たちは壊される家に歓声を上げる。絶望の中で、家が築かれ、生活の基盤が奪われていく。
教育も例外ではなく、大勢の兵士が学校に押し入り、生徒と教師を閉じ込めてしまう。希望の象徴だった学校がブルドーザーによって壊され、教育の機会をも奪われる。怯え、泣き叫ぶ子どもたち。すべてを失った人々は都市での生存を余儀なくされ、イスラエルの目的は人口を集中させることだ。2023年10月には、武装した入植者が再びマサー・フェルヤッタに襲いかかる。何も持たない人々は土地を離れ、それはフィクションのようでありながら、実際に存在する現実だ。この状況を見せつけられ、どう思えばいいのか、悩まされる。ユヴァルのようなユダヤ人もいることを知りながら、非人間化は避けるべきだと理解しているが、この現実には苦しむしかない。
正直、途中で観るのを諦めました。ブルドーザーで家を壊す場面には衝撃を受け、普通のいじめのように感じられました。家を失ったパレスチナの人々が洞窟に住むしかなくなる描写は、現実味が薄く時代遅れにも見えます。さらに、家を建てられないよう工具や発電機を没収し、取り返そうとしただけで撃たれる場面もありました。パレスチナの人々に対するイスラエル兵の蛮行はあまりにも過激で、私のストレス耐性では耐え難かったです。本来なら最後まで観るべきだと分かっているのですが、どうしても観ることができませんでした。
パレスチナの青年とイスラエルの青年が、国の因縁を超えてイスラエル軍の非道を記録し続けるドキュメンタリー。事前に情報は追っていたつもりでも、現実を映す映像は衝撃的だ。現在の現場で起きている事実を伝える、見るべき重要作。 #U-NEXT #キミシマムザ2025 #キミシマムザドキュメンタリーセレクト
パレスチナの迫害を描くドキュメンタリー。現代のホロコーストとも言われる過酷な現実を、理不尽さに胸を締め付けられるほど伝える。抗う術が見えないパレスチナの人々は、主にデモを行うかSNSで声を上げるくらいしか方法がない。日本やアメリカがイスラエルを支持しているとの見方もあり、因果応報の議論が交わされる。作品に関わった人々が拘束されたり、殺害されたという報告もある。
何のために行動しているのか、自分自身を疑問視してしまう。命令や決まり事に従っているだけなのか。
同じ人間とは思えない。住んでいる人たちに何の罪もないのに、この理不尽さは何なのか。
壊される理由さえわからないまま、ただそこにいる。
誰もが理解していない。誰一人として、どうすればいいのかわからない。
なぜ生きる権利を奪われなければならないのか。誰にもその権利はないはずなのに。
怒りの矛先を向ける場所も見つからない。誰に向けばいいのかもわからない。
理解できないからこそ声をあげる。多くの人に知ってもらい、その小さな権力を打ち砕かなくてはならない。
まるで空気を殴るように、答えは見つからない。ただ、どんな時でも民間人は何も悪くない。
イスラエル軍の破壊行為を発信し続けるパレスチナ人の若者と、彼を支えるイスラエル人の若者との勇敢な活動と交流を描いたドキュメンタリー。
イスラエル軍は無実の人々の家々や小学校、ライフラインを次々と破壊していく。ニュースでは想像もできない悲惨な現実が、リアルに映し出される。
この作品は、観た後に世界の見方を根本的に変えてしまうほどの力を持っている。
どんな理由があっても、人間の家を壊したり、銃で撃ったり、学校を破壊したり、手足を奪ったりすることは決して許されません。これは特定の国や宗教に属している人々だけの問題ではなく、全人類に関わることだと感じています。私には何ができるのでしょうか。