2019年8月2日に公開の映画「風をつかまえた少年」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「風をつかまえた少年」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
風をつかまえた少年が視聴できる動画配信サービス
現在「風をつかまえた少年」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「風をつかまえた少年」が配信中です。
| 動画サービスPR | 利用料金 | 視聴 |
|---|---|---|
|
今すぐ見る | |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
風をつかまえた少年のあらすじ
2001年、アフリカの最も貧しい国の一つ、マラウイが厳しい干ばつに見舞われる。14歳のウィリアムは、飢饉の影響で学費を払えず学校に通えなくなるが、図書館で手にした一冊の本をきっかけに、独学で風力発電の風車を制作し、干ばつに苦しむ畑に水を供給するアイデアを思いつく。村では今も雨を祈る人々がいる中、最愛の父でさえウィリアムの提案を受け入れようとしない。しかし、彼の家族を助けたいという揺るぎない決意が、徐々に周囲の心を動かし始める。
風をつかまえた少年の詳細情報
「風をつかまえた少年」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 原作者 | ウィリアム・カムクワンバ ブライアン・ミーラー |
|---|---|
| 監督 | キウェテル・イジョフォー |
| 脚本家 | キウェテル・イジョフォー |
| 出演者 |
|
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | ドラマ |
| 制作国 | イギリス |
| 公開日 | 2019年8月2日 |
| 上映時間 | 113分 |
風をつかまえた少年の公式PVや予告編動画
「風をつかまえた少年」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
風をつかまえた少年を見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
DMM TV

- 新作アニメ見放題配信数がトップクラス
- 業界最安クラスの月額料金
DMM TVは、DMMグループが提供する動画配信サービスで、「DMMプレミアム」に加入することで見放題作品を楽しめます。
配信作品数は20万本以上。アニメ・特撮・2.5次元舞台作品に強く、新作アニメの先行配信数は業界トップクラス。放送後すぐに最新アニメを視聴できる点は、アニメファンにとって大きな魅力です。さらに、DMM TV独占のドラマやオリジナルバラエティも充実しています。
月額料金は業界最安クラスの550円(税込)。14日間の無料体験に加え、新規登録で550円分のDMMポイントがもらえるキャンペーンも実施中です。コスパ重視で動画配信サービスを選びたい方におすすめのサービスです。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
風をつかまえた少年を無料で見る方法は?
「風をつかまえた少年」を視聴するなら、「U-NEXT」「DMM TV」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
風をつかまえた少年のよくある質問
-
Q映画『風をつかまえた少年』のあらすじはどのようなものですか?
-
A
『風をつかまえた少年』は、貧困と干ばつに苦しむマラウイの村を舞台に、若い少年が風力発電機を作り村を救おうとする物語です。実際の人物ウィリアム・カムクワンバの自伝が基になっており、創意工夫と希望の力を描いています。
-
Q『風をつかまえた少年』の主人公ウィリアム・カムクワンバの魅力は何ですか?
-
A
ウィリアム・カムクワンバは、逆境にめげず独学で電気の知識を身につける姿が魅力です。彼の不屈の精神と家族やコミュニティを守ろうとする強い意志が、多くの視聴者の感動を呼び起こします。
-
Q映画『風をつかまえた少年』のテーマやメッセージは何を伝えていますか?
-
A
この映画は、逆境に立ち向かう勇気と教育の重要性をテーマにしています。また、創意工夫やコミュニティの協力が変化をもたらす力を持っていることを伝え、多くの人にインスピレーションを与えています。
-
Q『風をつかまえた少年』の制作スタッフについて知っておきたい情報はありますか?
-
A
この映画は、監督兼脚本を務めたキウェテル・イジョフォーによって制作されました。彼は主演でもあり、映画化にあたってウィリアム・カムクワンバの実話を丁寧に描いています。
-
Q『風をつかまえた少年』はどのような評価を受けていますか?
-
A
『風をつかまえた少年』はその感動的な物語とリアルな描写が評価され、批評家からも高く評価されています。特にウィリアム・カムクワンバの実話に基づいているため、多くの視聴者の共感を得ています。



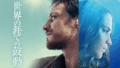
風をつかまえた少年の感想・評価
自転車のダイナモは、おそらく10V程度の発電能力しかないため、ポンプを回すのは非常に大変だったに違いありません。
高校の英語の授業で鑑賞した作品。廃材と自転車の部品を組み合わせて風車を作る少年の発想力と行動力には驚かされた。犬のシーンはあまりにも切なく、心に残る場面だった
水が出た瞬間、非常にテンションが上がった!
しかし、なかなか風をつかまえられない厳しい時間が続き、その間ずっと自分が多くの日本人と同様に恵まれていることを痛感した。欲しいものはお金を出せば手に入るし、教育だって当たり前のように受けられる。そんな状況下で、ウィリアムのように風車を作る自信は持てない。日常的に受けている授業から果たして本当に知識を得られているのか。その授業を受ける環境も大切だが、学びたいという意欲がなければ意味がないと感じた。
逆境に立たされたときこそ、人間の本当の力が試されると思う。あれだけ追い込まれた状況で冷静に策を考えられるウィリアムは本当に素晴らしかった。
2001年、マラウイのカムクワンバ家は干ばつによる貧困と飢えに直面していた。14歳のウィリアム(マクスウェル・シンバ)は学費を支払えずに退学するが、独学で風力発電を用いた灌漑のアイデアを思いつく。しかし、父親(キウェテル・イジョフォー)はこの考えを否定し、従来の農法を貫いて家族を守ろうとする。
本作はキウェテル・イジョフォーの監督デビュー作で、実際の出来事を基にした感動的な物語だ。
ウィリアムの奮闘が家族と村を救う爽快な展開がある一方で、約2時間にわたって厳しいマラウイの現状が描かれており、観るのはかなり疲れる。
題材の素晴らしさを考えると、風力発電の製作過程や、その成功の喜びを「北の国から」のようにもっと丁寧に表現してほしかった。
国家の無策がもたらす影響や、迷信、古い慣習を信じる大人たちが科学や若者の意見に耳を傾けない姿には、ため息が出てしまう。親たちの影響が若い才能を腐敗させているように思える。
父が息子を信じたことで、村は救われた。不特定多数の人を信じる必要はない。大切な人を信じることが、救いになるのだろう。
息子を信じた父の信念が、村を救った。広く人を信じる必要はない。大切な人を信じることこそ、救いになるのだろう。
村を救ったのは、父が息子を信じたその一念だ。不特定多数を信じる必要はない。大切な人を信じることが、救いへとつながるのだろう。
父が息子を信じたことで、村は救われた。多くの人を信じる必要はない。大切な人を信じる力が、救いを生むのだろう。
風をつかまえた少年は、干ばつと洪水に翻弄されるアフリカの大地で、知恵と仲間の力で未来を切り開こうとするウィリアムの物語。現実は厳しいものの、希望は必ずどこかにあるというメッセージを多くの人が語り継いでいます。教育と家族、友情、困難への挑戦が織り成す感動の実話映画です。
賛同の声(抜粋)
– 加藤登紀子(歌手):洪水と干ばつに揺れる大地で生きる人々の、愛と希望に満ちた物語。現実は厳しいけれど、どこかに可能性があると信じたい。
– 鎌田實(医師・作家):見事な切り口で、観る者の生きる勇気を引き出す。希望の映画だ。
– 木村草太(憲法学者):知らないことを学ぶ楽しさと、未来をつくる学びの原点を再確認できる。マラウイを知る喜びも大きい。
– さくまゆみこ(『風をつかまえたウィリアム』訳者/アフリカ子どもの本プロジェクト代表):干ばつと飢餓の中で、諦めず工夫して未来を切り開くウィリアムのエッセンスを伝える。日本の子どもたちも力を得られるだろう。
– 鈴木福(俳優):飢餓に苦しむ人々を助けたいという思いが、友人・家族の協力で現実の奇跡を呼ぶ。日々の幸せを再認識させてくれる作品だった。
– 滝藤賢一(俳優):子どもは感じ、考え、生きるエネルギーに満ちている。大人としての責任を見つめ直させられる。
– 中江有里(女優/作家):ウィリアムの知恵と発想が、困難の中で未来を築く力を示す心温まる物語。
– 藤原和博(教育改革実践家):村には電気も学校もなかったが、独学と発電機づくりなど創意工夫の原点がここにある。
– 堀潤(キャスター/ジャーナリスト):学ぶことは生きることの根源。知識と技術があれば誰もが自分の力を生み出せる、という力強いメッセージ。
– 増田ユリヤ(ジャーナリスト):風車づくりを通じた村の協力が、マラウイの風を受けて人々の心を回し続ける。
– MISIA(歌手):教育は未来への希望。長年の教育支援活動にも深く共鳴する、夏にぜひ観てほしい一本。
– 茂木健一郎(脳科学者):冒頭の美しい風景から観る者を惹きつけ、学びの意味を描ききる傑作。
– 安河内哲也(英語講師):見終えた後、学ぶ目的がはっきりと見える。若い世代に特におすすめの作品。
– 安田菜津紀(フォトジャーナリスト):世界の矛盾を越え、人々の力と知が響く。その機会を与える映画。
– 山崎ナオコーラ(作家):父親の視点が心に響く。子どもが新しいことを学ぶとき、応援する親でありたいと改めて感じた。
– ヨシダナギ(フォトグラファー):教育と安全が整えば社会は根づく。風をつかまえた少年は、貧困という壁を越える希望を世界へ運ぶ。
– 米村でんじろう(サイエンスプロデューサー):限られた資源の中での創意工夫が、世界中の子どもたちに新しい風を吹かせる。
この映画は、学びと知の力が未来を切り開くことを強く伝えます。風とともに生きる人々の物語は、観る者の心に希望の種を蒔き、世界に小さくても確かな変化を起こします。夏休みの一本として、教育と未来を見つめ直す視点を提供してくれる作品です。
【Return to Africa】マラウイ共和国を舞台にした実話を基にした作品で、タイトルから結末を予想しやすいものの、マラウイの貧困事情を深く描写しており、非常に見応えのある内容になっています。ストーリーは、困難な環境にも負けず、知恵と才覚で家族と村を救った少年の成功物語。文科省選定や厚労省推薦もあり、子供向けの側面も持ちつつ、宗教観や世代の価値観、貧困問題、男女差別、圧政など多岐にわたるテーマが組み込まれています。特に「教育」の重要性が強調されています。時代背景が2965年という設定でなければ、1950年代の話と誤解されるかもしれませんが、ラジオから流れる9.11のニュースを聞くと、21世紀の今でもアフリカの遠い地でこのような生活が続いていることに気づかされます。さまざまなことを考えさせられる佳作です。
主人公ウィリアム・カムクワンバが知識を得て風車を作る過程に重きを置くことで、エンターテインメントとしての魅力が増したかもしれませんが、マラウイの情勢に描かれる暗い面が際立ちます。教育の重要性がメインテーマで、農作業の過程が章立てのように映像に現れ、単なる作物の話に留まらず、子どもたちを育てるプロセスとも関連していると感じました。つまり、ウィリアムの父トライウェル(キウェテル・イジョフォー)は、すべてに失敗したと責められるシーンがあるものの、好奇心旺盛な息子ウィリアムを育てた点では、次世代という作物の育成に成功していたのかもしれません。飢饉と学費の問題でウィリアムが学校を退学せざるを得なかったが、彼は最後に大きな成果を上げるのです。
それにしても、廃品や自転車部品を用いて作る風車は、個人の小さな寄付で賄える品々です。こうした資源が手に入らない国家が21世紀にも存在することには驚かされます。一方で、近代化と民主化がもたらした制度や資本の原理は、人々を土地に縛り付け、自由な移動を妨げ、精神的な荒廃を生んでいるとも考えさせられます。映画の冒頭と結末には葬儀のシーンがあり、片方はキリスト教、もう片方はイスラム教で行われますが、最終的には土着信仰やアニミズムを象徴する独特の衣装を纏った「お迎え」が登場します。これは、自然から乖離しない生き方を忘れないようにという教訓を孕んでいるのかもしれません。舞台がアフリカということもあり、観賞後に深く考えさせられる作品でした。Return to Africa!
素晴らしい!
言葉選びに感じる重みがあるけれど、キウェテル・イジョフォーの
話し方が圧巻だ。
視聴しながら色々な思考が浮かんだ。
・この事態は地域の気候特性によるものなのか?
・「魚の捕り方」以上に「魚」そのものが重視されているのか?
・教育の重要性を改めて実感した。
・「米百俵」的な視点を持つ指導者は存在しないのか?
・日本でも飢饉や飢餓はあったが、何故このような状況には至らなかったのか?
・このような気候的ハンデを抱えた地域が人類誕生の地となった理由は何なのか?
科学が人を救う物語。諦めず息子を最後まで信じた美しい妻が選んだ道は間違いなかった。二人が結婚して生まれた立派な息子を学校へ通わせることは、父親の功績だ。食料が尽きると人の行動は予測できなくなるため、現実味がありすぎて怖かった。娘が餓死の不安におそわれたとき、お母さんは腕を食べても娘を守ると覚悟を決め、圧巻だった。
過酷な環境から抜け出そうとする熱意やアイデアは、恵まれた普通の人には到底発想できないことだろう。
「知」を追求する姿勢は誰にも奪うことができない。
この種の実話ベース映画が好きです。風車の開発よりも、マラウイの社会・環境問題と、それに立ち向かう家族愛が主題として描かれており、まさに勇気をもらいました。
少し気になる点はあったが、それでも4.5点をつけたい。元の『風車を作った少年』というエピソードを知っていたので、前のめりで観賞。飢饑や貧困の描写が強く、無学な父親との確執も丁寧に描かれる一方、この映画の核となる風車を作るアイデアの描写はやや薄かったのが残念だった。作中の水が湧き出るような感動を、もう少し短い尺で何度も味わえればよかった。とはいえ、学費未払いにも関わらず図書館に足を運ぶハングリー精神は強烈で、成功へと結びつく描写は称賛したい。