2019年9月13日に公開の映画「サタンタンゴ」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「サタンタンゴ」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
サタンタンゴが視聴できる動画配信サービス
現在「サタンタンゴ」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「サタンタンゴ」が配信中です。
| 動画サービスPR | 利用料金 | 視聴 |
|---|---|---|
|
今すぐ見る | |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
 |
|
今すぐ見る |
サタンタンゴのあらすじ
Satantango(サタンタンゴ)は、クラスナホルカイ・ラースローの同名小説を原作とする長編映画。舞台はハンガリーのとある村。降り続く雨と泥に覆われ、活気を失ったこの村に、死んだはずの男イリミアーシュが帰還する。彼の帰還に惑わされ、さまよう村人たち。イリミアーシュは救世主なのか、それとも――。全編約150カットの驚異的な長回しで描く野心作。
サタンタンゴの詳細情報
「サタンタンゴ」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 監督 | タル・ベーラ |
|---|---|
| 脚本家 | クラスナホルカイ・ラースロー タル・ベーラ |
| 出演者 | Éva Almássy Albert デルジ・ヤーノシュ ホルヴァート・プチ ルゴシ・ラースロー ヴィーグ・ミハーイ |
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | ドラマ |
| 制作国 | ドイツ スイス ハンガリー |
| 公開日 | 2019年9月13日 |
| 上映時間 | 438分 |
サタンタンゴの公式PVや予告編動画
「サタンタンゴ」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
サタンタンゴを見るのにおすすめの動画配信サービス
U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる
- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる
- 無料体験で気軽に試せる
U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。
見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。
また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。
DMM TV

- 新作アニメ見放題配信数がトップクラス
- 業界最安クラスの月額料金
DMM TVは、DMMグループが提供する動画配信サービスで、「DMMプレミアム」に加入することで見放題作品を楽しめます。
配信作品数は20万本以上。アニメ・特撮・2.5次元舞台作品に強く、新作アニメの先行配信数は業界トップクラス。放送後すぐに最新アニメを視聴できる点は、アニメファンにとって大きな魅力です。さらに、DMM TV独占のドラマやオリジナルバラエティも充実しています。
月額料金は業界最安クラスの550円(税込)。14日間の無料体験に加え、新規登録で550円分のDMMポイントがもらえるキャンペーンも実施中です。コスパ重視で動画配信サービスを選びたい方におすすめのサービスです。
Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ
- コスパの良い料金プラン
- Amazonのプライム会員特典が利用できる
Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。
プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。
料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。
サタンタンゴを無料で見る方法は?
「サタンタンゴ」を視聴するなら、「U-NEXT」「DMM TV」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
サタンタンゴのよくある質問
-
Q映画『サタンタンゴ』のあらすじはどうなっていますか?
-
A
映画『サタンタンゴ』は、ハンガリーの田舎を舞台に、社会主義体制の崩壊に直面する人々を描くドラマです。イシュトヴァン・タル監督が手掛けており、その日常と崩壊のプロセスが静かに描かれています。重要なテーマが、希望と絶望の交錯する生活の中で展開されます。
-
Q『サタンタンゴ』の主要なキャラクターについて教えてください。
-
A
『サタンタンゴ』では、イリミアシュという神秘的な人物が中心的な役割を持ちます。彼は村の住民によって救世主のように迎えられるが、実際には彼の行動が事態を複雑にします。また、住民たちの間の緊張と葛藤を通して、彼らの人間関係が詳細に描かれます。
-
Q『サタンタンゴ』のテーマやメッセージは何ですか?
-
A
『サタンタンゴ』は、崩壊しつつある社会体制を背景にした絶望と希望のテーマを探求しています。物語は人間の孤独や、自己欺瞞、希望への微かな渇望を描いています。特に無力感や閉塞感を感じさせる環境が観る者に強い印象を残します。
-
Q映画『サタンタンゴ』の制作スタッフについて知りたいです。
-
A
『サタンタンゴ』は、イシュトヴァン・タルが監督を務めた作品であり、彼の特徴的な長回しの撮影手法が多用されています。撮影監督のガーボル・メダヴィルツは、この作品で陰鬱な雰囲気を巧みに演出しています。また、音楽はミハイ・ヴィグが担当しています。
-
Q『サタンタンゴ』の評価や人気の理由は何ですか?
-
A
『サタンタンゴ』は、その独特の映像美と深遠な内容から高い評価を受けています。特に映画の長尺なランタイムと、それに見合う詳細なストーリーテリングが、映画ファンの間で称賛されるポイントです。また、その挑戦的なスタイルが映画芸術の可能性を広げたとして評価されています。
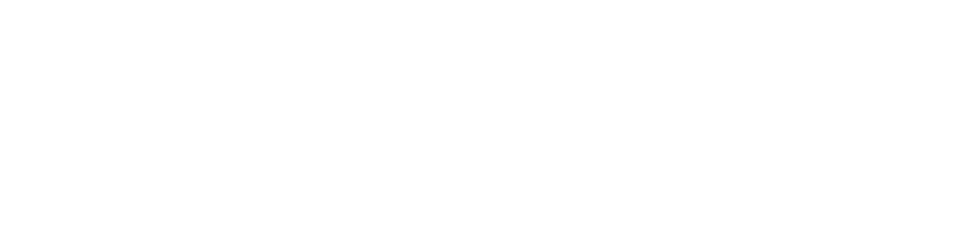



サタンタンゴの感想・評価
僕たちが映画に求めるものは人それぞれ異なるとしても、100人という条件を仮に立てたときにも、必ず共通して見いだせる核があるはずだ。それは映画以外の領域からは容易には手に入らない、貴重で普遍的な何かだ。
この核を普遍性、あるいは本質と呼ぶことが多い。さらに、100人がそれぞれ手にした100の作品を100回ずつ観たとき、おおむね共鳴する点があるなら、それこそが本質的で普遍的な要素といえるだろう。
映画という表現形式の中に宿る本質(普遍性)とは何なのか。そう問いかける作法は、巨匠たちの代表作を含む作品群の中でさまざまな答えや問いを生み出し、評論家や愛好家たちもそれぞれの作品を参照しながら語っていく。
結局のところ、それらを煎じ詰めれば、動く絵が作り出す幻想の中で空間と時間を再構成する、というリミックス的方法論に行き着くのではないか。四次元的な(三次元+時間)幻想を、幻想であると自覚しつつ幻視する官能こそが、映画の本質的な体験へと結びつくのだ。
時間も空間も、解体され再統合(リミックス)されることで、真に映像らしくなる。だからこそ、長回しという手法が用いられるのだろう。
長回しによって喚起されるのは、現実を現実として認識する瞬間において、実際には手元の対象を何も正しく見ていないという逆説だ。空間と時間の純粋な描写が長く連なれば、観客は暴力的ともいえるまでにスクリーンへと引きつけられ、初めてその事実に気づく。こうした体験は、暴力性と同時に現実離れした官能として立ち現れることがある。
そこへ集約された代表作が、439分(7時間19分)という上映時間になる。
だからこそ舞台は匿名性の神話性を帯び、映像はほとんどが白黒で描かれる。圧倒的に美しい構図と役者の動線は、この暴力的な官能のためにこそある。ドラマは必須ではなく、抽象的な不吉さと美しい緊張だけで映画は成立する。
イリミアーシュと呼ばれる人物は、基本的にはドラマのために造形された存在というより、村人たちが幻視を通じて初めて現実を現実として認識する、人間の普遍的な原理をスクリーンに投影する存在として描かれている。
あるいは、第二次世界大戦中にナチスの枢軸国として戦い、戦後にはソ連の衛星国となった背景を、暗喩として提示しているとみなせる節もある。
ハンガリー
監督の母国・ハンガリーを舞台に、中高年で子どものいない複数の夫婦が共産党時代の寒村で暮らす姿を描く。壁は剥がれ、空き家が目立つ貧困と荒廃の風景の中、農民たちは酒場と不倫にしか居場所を見いだせない。そんな村に、死んだはずの人物が戻ってくる。彼は突然、農民を豊かにするという移住計画を掲げるが、具体性は霞んだままだ。とはいえ農民たちは彼に翻弄されながらも、全財産と生活のすべてを委ねてしまう。7時間を超える長尺の映像が続くなか、これから何かが始まる予感だけが濃く残る。セリフのないまま執拗に繰り返される人物描写や、雨の中を闊歩する場面が、この映画の象徴として浮かび上がる。最後には、文脈を問わずトルコ軍が攻めてきたと叫ぶ場面が挟まれ、ハンガリーの歴史の疼きを露わにする。未知の勢力がどこからともなく現れる荒涼とした大地で生きてきたハンガリーの本質を、映画は映し出しているのかもしれない。
2025年ノーベル文学賞を受賞したハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー。彼の同名小説を原作に、ハンガリーの映画監督タル・ベーラが7時間18分の長編映画として映像化した『サタンタンゴ』。
舞台は、町から遠く離れた湿地に囲まれ、雨が続くと外界との往来が困難になる村。電気や水道も整っておらず、外壁は剥がれ、穴の空いた家が点在する。住民たちは貪欲と不信、淫欲に染まり、未来は最もおざなりにされている。秋の長雨が始まるある日、死んだはずの男イリミアーシュが帰ってくるという噂が村を覆す。困惑・動揺・激昂やがてその日の終わりにはひとつの悲劇が起きる。イリミアーシュは村人と遺骸を前に口にする救いの導きか、それとも悪魔のささやきか。
上映は三部構成で、各部の間に休憩が挟まれる。合計およそ8時間。昼頃に劇場へ入れば、出てくるときにはすっかり夜。長回しが基本の演出で、村人が酒に溺れて踊り続ける場面は約10分にも及ぶなど、ほぼ全カットが長尺だ。
雨の描写が作品の核を成す。目的を持つ足取りで降る雨を喜ぶ者もいれば、屋根のない車の荷台で未来に背を向け、黙って雨に打たれる者もいる。特に後者は、出荷された家畜のようにも見える。絶望の中でほのかな希望へと群衆が惹きつけられる場面が多く、そんな群像の中で自らの足で歩む選択をする一人の姿が非常に示唆的で、個人的にも特に印象深い。
そして、希望を自ら掴むこともせず、ただ沼地へ静かに沈むかのように傍観する男の姿で物語は幕を閉じる。
「終末的な恐怖のただ中にあって、芸術の力を再確認させる、説得力と先見性のある作品群」と評され、ラースローはノーベル文学賞を受賞した。改めてこの『サタンタンゴ』を観ると、「芸術の力」は決して希望のみを描くものではないと感じる。終末の恐怖の中で人はどう動くのか、動かないのか、そして自分をどう見つめ直すのか。
2026年には国書刊行会から翻訳書が刊行される予定。映画だけでは読み解ききれない描写もあり、小説を手に取り、終末的な世界の中で自分を深く模索したい。
438分も知らずに見てしまった!
頑張ったよ!
疲れた
長いカットが延々続く。
最初は牛のシーンと窓だけ。
歩くシーンはずっと歩き続けるのを見るんだ。
参ったよ(*´д`*)
原作が今年のノーベル文学賞を受賞した作品ということで、映画化されると知り軽い気持ちで視聴を始めたら、なんと438分もある作品でした!タル・ベーラには支持者が一定数いるようですね。独特のシュールさがあり、6日間かけて観ましたが、内容を理解するのが難しい部分もありました。シュール表現は新鮮な印象を受けました。「ニーチェの馬」も良かったのですが、こちらは156分。映画館で最後まで観ることができる人には敬意を表します。イメージフォーラムでの上映時間も挑戦的で、13:15スタートで20:38終了とは!正直、コメントするのが難しい作品でした。
#サタンタンゴ
本物のサタンと魔術が描かれているため、ダークウェブへと誘われる。
悪魔と人間は共依存の関係にある。
ハイパーリアリズムによって映し出される日常は、愚鈍な踊りのようにサタンに捧げられる儀式となる️円環に囚われた暗黒の祭典。
心の中にあの灰色の町が築かれた。
このどうしようもない恐怖や怒りを、いつでもサタンに捧げる準備は整っている。
さようなら。くるくると回り続ける移動と収束の反復は、私たちを次々と酔わせる。個性を欠く人々の群れと魔術師イリミアーシュが織り成す、六歩進んで六歩戻る七時間十八分の世界。永遠あるいは無限と捉えられるタンゴの迷宮を抜けることができない者たちに、結末はサタンの名の下に機能停止を迎えるように見える。しかし、そこにこそカタルシスが宿るのだ。旧約聖書を土台にした十二章の脚本は、上から見れば円環、横から見れば各プロットが立体的につながる構図として立ち上がる。どこから切り取っても入口は始まりであり終わりであり、終わりはまた始まりへと回帰する。ウロボロス的な循環を描くこの構造には出口がなく、観客は終始、絶望に打ちひしがれるだろう。国家が神の与えし無限の反復から脱出できるのか、ニーチェ的永劫回帰からの離脱は可能なのか。人類が自意識を超えたとしても、繰り返しの実存から逃れることはできるのか。タルベーラ監督の挑戦を、視覚と身体と心で確かめてほしい。
以下はネタバレを含む映画の解体だが、前半の六章は、帰還前のイリミアーシュ(魔術師)をさまざまな視点で描く。後半の六章は、彼の帰還によって起こる出来事を淡々と見せ続ける。要点を微細にまとめれば、次のようになる。物語は、魔術師の帰還の噂に惑う村人の様子を描く一章、帰還のきっかけとなる警察との駆け引きを描く二章、窓の外を見つめて何かを記録する酔漢の医師を描く三章、村人たちが復活を語る四章、支配構造の本質を示す少女の動物虐待を描く五章(本作で最も批判が集中した場面)、全員が食堂に集まり無限のタンゴを踊り続ける六章、キリストのように復活したイリミアーシュが少女の死を用いて村人を扇動する七章、村人たちが新天地を目指す八章、裏で蠢くイリミアーシュの真の顔を描く九章、不審を感じた村人を黙らせて離散させる十章、村人についての報告を警察が延々とタイピングする十一章、鐘の音とともに世界を閉じる見捨てられた医師の十二章だ。長尺の偶像劇でありながら登場人物は多くなく、タンゴのステップのように同じ箇所を定点的に巡回しつつ物語は進む。数時間の集中力を保てば、この魑魅魍魎とした世界を支配する三人のキーパーソンに気づくはずだ。まず第一に、預言者エレミヤことイリミアーシュ。原典『エレミヤ書』は旧約聖書の三大預言書の一つで、バビロンの征伐と流浪を描く。十一章で判明するエリミアーシュの正体は、村人を離散させるため政府から送り込まれたスパイと結びつく。次に二番目は、最も異質とされるアル中の医師。彼は劇中、直接の面会を避け窓越しに世界を観察する全能の神として機能する。すべてを見守り記録するが、救済には動かない宿命の象徴だ。そして最後に三人目、村人の中で浮いた存在のフタキ。彼だけはイリミアーシュの言説に囚われず、仮構の理想郷から離脱するべく自ら直談判で実践的な選択をする。神のような傍観者にも、崇拝者の立場にも属さない。永劫回帰の円環から脱退に成功した唯一の人物かもしれない。盲目的に理想を信じなかったフタキの勇気こそ、宗教的価値が崩壊したこの時代を照らす灯火となり得るのだろう。
この物語の全体像を理解するには、フン族と呼ばれる諸説ある民族が社会主義時代に直面した抑圧と混乱を深掘りすることが鍵になる。富や資源、そして人々の情熱までもが中央集権によって搾取され、希望を失った四十年間の鬱屈が画面の隅々に染み出している。財の奪い合い、命の奪い合い、愛情の奪い合い抑圧者と被抑圧者の構図に未来は見えず、亡命を選ぶ人々もまた移動禁止令により自由を奪われてしまう。イリミアーシュは労働者の弱みにつけ込んだ権力の象徴と捉えられる。ベーラ監督にとって、当時はまさに世紀末的な時代だったはずだ。鐘の音が木霊するたび、彼の精神は閉じ込められたままで、今なお抜け出すのが難しいのかもしれない。しかし現代のリゾーム的な実存のあり方を考えると、第二第三のフタキが世界的に現れるのは必然の趋势だろう。ちなみにこの映画を高く評価する人々の多くは、七時間十八分を無駄にはしたくないと考える実利的な思考の持ち主であることが多い(私も含む)。
ノーベル賞受賞作を鑑賞しました。
荒れ果てた農村の貧しい日々を描いていますが、映像は非常に上品で、心に響きました️
ストーリーも素晴らしく、満足できました️
鑑賞というより対峙・対決の体感だったが、劇場で味わえたことは幸いだった。正直言えば上映は長く、体力も消耗する。途中には冗長に感じる場面もあった。しかしタル・ベーラの驚異的な長回しには慣れてくると、長さが苦痛にならず、ただ次の展開を知りたくて引き込まれた。最初の約2時間、3つめの節あたりは長回しのカットが堪えたが、徐々に自然と情報量の多さと映画の奥深さに目を奪われていった。とはいえ、モノクロ・字幕付きという条件は現代の目にはかなり厳しく、目が疲れ、瞼を閉じたくなる瞬間が増えた。現代人の目には優しくない作品だと感じた(笑)。ただ途中の休憩があったおかげで、身構えずに観続けられたのは良かった。唯一の反省点は、水分補給を水で済ませてしまったこと。次回はお茶か紅茶でカフェインを取りつつリフレッシュして臨みたい。
B級映画の究極。世の中で最も無意味な存在。称賛も非難もすることなく、ただそこにある映画。
7時間以上。昨晩20時から見始め、睡眠を挟んで本日午前中に鑑賞を終えた。最初はこの長さに構えていたが、気がつけばあっという間に終わっていた。ワンカットが非常に長く、カット数も少ない(150カット)ため、ゆったりと深く作品の世界に没入できた。また、顔のアップが多用されているため、キャラクターへの愛着も自然と強まる。
作品には多くの謎が残されているが、ストーリー以上に作品の世界観や役者のリアリティが際立っており、それを眺めているだけで楽しめる。監督の卓越した技術には圧倒されるばかりだ。
村人の救済の物語なのか、それとも大きな詐欺に巻き込まれるのか。ラストで少し示唆されるが、真相はどうなのか。
原作者がノーベル文学賞を受賞したのは素晴らしいことだ。本作が日本語に翻訳された際には、ぜひ読みたいと思う。
原作者がノーベル文学賞を受賞したこともあり、プライムで視聴してみた。作品は非常に長大だが、構図の美しさや効果的な音響、緊張感のある雰囲気が印象的で、飽きずに楽しめた。人物を映すカットは絵画のようで、神秘的な印象を受ける。寓話的な要素やハンガリー特有の背景、物語の詳細な解釈は理解できていないが、とにかくこの映画が好きだった。
映像や音、映画の技法が豊富に盛り込まれており、非常に楽しめる作品だった。タンゴを踊る中で、おでこにパンをのせている人が印象に残った。
・長尺であるため視聴を躊躇していた作品だった。約1年ほど観賞を先送りしていたが、ノーベル文学賞を受賞したクラスナホルカイ・ラースローの話題に背中を押され、決意して観賞。・この映画はキリスト教文化圏の観客には意味を読み解く楽しさがあるのだろうと感じつつも、個人的にはやや消化不良だった。作中でイリミアーシュは聖人のように描かれ、村は「終わったソドム・ゴモラ」として描かれているらしいが、それ以上の要素は掴めなかった。・白黒、廃墟、長回し。殺伐とした東欧の空気感が際立ち、タルコフスキーの『ストーカー』『ノスタルジア』を思わせる。
12章で構成されているから、リミテッドシリーズのように見れば完走できるかもしれないと思った。しかし前半の6章は時間が逆戻りする展開が多く、非常に長く感じた(ガス・ヴァン・サントの『エレファント』がこれを模倣したのか?)。前半の劇的なエピソードでは、猫がさすがに驚かされるだろう。
7章から物語が動き始めるが、まだ3時間も残っているのか…。決して難解でもつまらないわけではないが、体力的には大変だ。
そしてラストだが、これは夢オチのような感じなのか?7時間19分もかけて?それは伝説になるよな。
今回のノーベル文学賞を受けて、クラスナホルカイの原作の翻訳が国書刊行会から来年出るみたいなので、読んでみようかな。