2021年10月2日に公開の映画「カナルタ 螺旋状の夢」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「カナルタ 螺旋状の夢」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。
カナルタ 螺旋状の夢が視聴できる動画配信サービス
現在「カナルタ 螺旋状の夢」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「カナルタ 螺旋状の夢」が配信中です。
カナルタ 螺旋状の夢のあらすじ
セバスティアンとパストーラは、エクアドル南部のアマゾン熱帯雨林に暮らすシュアール族。かつて首狩りの伝承で恐れられたとされるシュアール族は、スペインの植民地化を経ても武力征服を受けず、独自の文化を守り続けてきた民族として知られる。口噛み酒を交わしつつ日々森へ分け入り、生活の糧を得る一方で、彼らはアヤワスカをはじめとする覚醒植物がもたらすヴィジョンや、自ら発見した薬草の知識によって、世界の捉え方を柔軟に更新していく。変化する森との関係の中で、自己の存在を新たに紡ぎだしていく。
しかし、ある日彼らに試練が訪れる。映像人類学の世界的拠点として評価される英・マンチェスター大学で博士号を取得した気鋭の監督が放つ渾身の長編ドキュメンタリーは、従来の枠を超える独自の表現で新境地を切り開く。
カナルタ 螺旋状の夢の詳細情報
「カナルタ 螺旋状の夢」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。
| 監督 | 太田光海 |
|---|---|
| 出演者 | セバスティアン・ツァマライン パストーラ・タンチーマ |
| カテゴリー | 映画 |
| ジャンル | ドキュメンタリー |
| 制作国 | イギリス 日本 |
| 公開日 | 2021年10月2日 |
| 上映時間 | 121分 |
カナルタ 螺旋状の夢の公式PVや予告編動画
「カナルタ 螺旋状の夢」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。
カナルタ 螺旋状の夢を無料で見る方法は?
「カナルタ 螺旋状の夢」を無料で視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。
「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。
カナルタ 螺旋状の夢のよくある質問
-
Q映画『カナルタ 螺旋状の夢』のあらすじは?
-
A
映画『カナルタ 螺旋状の夢』は、幻想的なストーリーが特徴のサイコスリラーです。主人公は、夢と現実が交錯する不思議な世界で、螺旋状に繰り返す不気味な出来事に立ち向かいます。彼が乗り越える試練を通じて、自身の内面を探る旅が描かれています。
-
Q映画『カナルタ 螺旋状の夢』のテーマは何ですか?
-
A
映画『カナルタ 螺旋状の夢』は、自己探求と現実の曖昧さをテーマにしています。主人公が直面する夢の中の出来事を通じて、視聴者は現実とは何か、自己とは何かを考えさせられます。視覚的な美しさと哲学的な深さが融合した作品です。
-
Q『カナルタ 螺旋状の夢』の見どころはどこですか?
-
A
『カナルタ 螺旋状の夢』の見どころは、その独特な映像美と心理描写です。幻想的な映像と繊細に描かれたキャラクターたちが、観る者に強い印象を残します。特に夢と現実がシームレスに繋がる演出が秀逸です。
-
Q『カナルタ 螺旋状の夢』のキャラクターの魅力は何ですか?
-
A
『カナルタ 螺旋状の夢』のキャラクターは、それぞれが複雑で深い内面を持っています。主人公の成長と葛藤が丁寧に描かれており、彼の感情の変化が観客に共感を与えます。また、サイドキャラクターも多面的で、物語に厚みを加えています。
-
Q『カナルタ 螺旋状の夢』の制作スタッフについて教えてください。
-
A
『カナルタ 螺旋状の夢』は、ビジュアル表現に秀でた監督と才能あるスタッフによって制作されました。撮影技術や音楽の選択など、細部に至るまでこだわり抜かれた作品で、視覚的にも聴覚的にも楽しめる映画です。
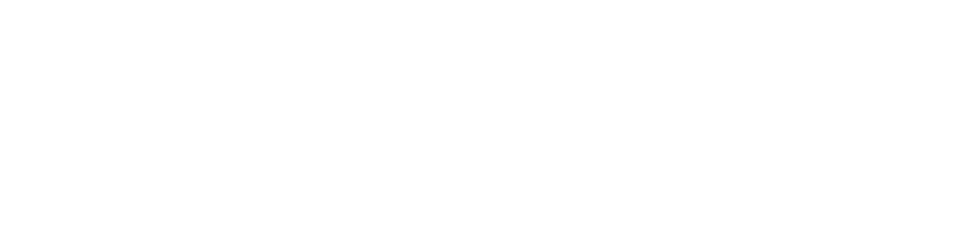






カナルタ 螺旋状の夢の感想&レビュー
監督のトークショーに参加してきた。とても興味深かった。昔ながらの伝統を守る部族とは異なり、未来に伝統となるものを今この瞬間から形にしているように感じた。さらに、こうした場にも西洋の文化やテクノロジーが入り込んでいて、いずれは大きな変化を生み出すのだろう。
旅行先での長尺なホームビデオには、文化人類学的な新味は感じられず退屈だった。これだけ演出しておきながら、彼らの文化に触れたと自負する監督は、相当裕福なブルジョワに違いない。現地の人々に金持ち呼ばわりされているのを見て、呆れた。
将来のビジョンを描きながら、息子を学校へ通わせるために働き、森を手入れし、料理を作り、冗談で笑い合い、夢を追い続ける。そんな暮らしは誰にとっても特別なものではなく、私たちは誰しも日々の現実に縛られて生きていると感じる。できるだけ地産地消を心掛け、過剰なプラスチック包装を避け、輸送費を抑え、地球に優しい生活を学びたい。自分で家を作るのはやっぱりかっこいい。よく分からない錠剤をむやみに盲信するのではなく、自分の舌と体で確かめた薬草を信じるほうが、私には自然で正しい選択のように思える。自分の感覚をもっと信じてもいいと感じる。喉が渇くと竹を削って水を飲むそんな暮らしをいつか実現したい。
彼らは時空を超えた世界とつながっている。アマゾンで生まれた夢は、都市で暮らす私を新たな世界へと導く。未来を見据えるこの映画は、私たちに新しい視点を与えてくれる。太田光海という才能に出会えたことを嬉しく思う長谷井宏紀(映画監督『ブランカとギター弾き』)
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
映画「カナルタ」を観た後のメモ
死者は息を吹かない。息を吹くとは、よみがえりを意味するほど生の力を身体に満たす行為だ。映画の中で印象的だったのは、シュアール族のセバスティアンが見せる息を吹くさまだった。彼がアヤワスカのビジョンを見ているとき、歯へ向けてあちこちに息をフーーッと吹きかける。空中に浮くように雲を蹴散らすような動きで、恐怖に押しつぶされそうなときもここにいる、生きていると息を吹く。自分を脅かす動植物や霊に対して、土地を主張するように息を整える。
口噛み酒のチチャを作る場面では、妻のパストーラがユカを噛み、鍋に吹きかける場面が印象的だ。吐くのではなく、吹くのだ。吐くときは不要なものを排出する行為、吹くときは命の息吹が体から躍り出る瞬間だ。だからこそ美味しいチチャになる。
映画を見終えたあと、東京の電車の中で見知らぬ人々がマスク越しにつくるため息を感じる。切なくも神秘的な光景だ。いろいろな出来事があり疲れも溜まるが、それでもこの身体にはまだ生命力が宿っている。負けていられない、前に進もうという気概があふれてくる。
生命力を再確認する瞬間だ。
映画を扉として、シュアール族の人々と個人的に出会えたような気持ちを味わわせてくれてありがとうコムアイ
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
凡庸な受け手は、撮影者・太田光海と被写体セバスティアンの間に理解が成立していると解釈しがちだ。しかし、ラスト近くのアヤワスカの場面を含む随所には理解の不均衡が露呈する。原住民の文明的な装いと、撮影者が東洋の文明圏出身であるという見かけだけを見過ごすと、そこには不穏さが浮かび上がる。未規定なものを呼び込む徴候が、すでに私たちの日常にも頻出している。目を凝らそう宮台真司
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
映画『カナルタ』に寄せて
カメラを手にした人類学者=I人類学者が、植物の内面空間へと足を踏み入れる。カメラに映る液体が森のすべての生き物を生かし、癒し、超越の扉を開く。カメラは植物の外部にあるが、それが捉える映像は確かに植物の内面へと入り込んでいると私たちは感じる。映像による人類学は、この映画を通じて自然の奥深さへさらに踏み込むことに成功した中沢新一
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例えば、徹底的に消毒された私たちの手は、どんな微生物も受け付けず、体内で生まれる微生物を誰にも届けない。一方、芋に唾液を混ぜて酒を作り、その酒を振る舞って家を建てる。吐瀉物は土へ還る。そうして全身を使って大地と対話し、素朴な循環を続けるアマゾンの人々。どちらが地球とともに生きていると言えるのだろう森山未來
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
植物のおかげで人は生きてきた。忘れてはいけない。人間の始まりから変わらず、森を歩き、森で歌い、森の水を飲む暮らしに混ざると、強くよみがえるのはこの事実だ。薬草マイキュアが示してくれるのは、あなた自身の真実だ。ナンキが撮ったこの映画が、私たちにとっての薬草となる管啓次郎(詩人・明治大学教授)
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
新しい才能が放つ、力強い力作である。文明化によって人間が失ってしまった多くの能力を痛感させられる。「森を壊すことは、自分を壊すことだ」という主人公の言葉は、全人類が胸を張って耳を傾けるべき金言であり、普遍的な警鐘であり、予言である想田和弘(映画作家)
________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#声_長谷川宏紀#声_コムアイ#声_宮台真司#声_中沢新一#声_森山未來#声_菅啓次郎#声_想田和弘
冒頭のチチャは圧倒的だった。植物と共生する情景が印象的で、最初の虫のインサートはヤノマミを彷彿とさせる。どの時間軸で構成され、どれくらいの尺を撮影したのだろう。毎回どれくらいの狙いを持って望んでいるのか。工夫されたカメラワークとは何か。
太田光海さんへのリスペクトを感じる一本。アヤワスカやマイキュアといった体験を追体験するような感覚に包まれたが、実際には経験したことはない。セバスティアンを含むシュアール族の営みの全てがピュアで、私もピュアに生きようと思えるようになった。終盤へと濃くなる観察者の影の描写や、映像の切り方、語りの使い方など、映像人類学の視点からも学びの多い作品だった。#buff2024
ドキュメンタリー映画を鑑賞しました。アマゾンに暮らすシュアール族の生活を深く切り取った内容で、口噛酒やアリを使った治療法など、珍しい光景が多く見られました。ただ、全体的には雰囲気重視な印象を受け、少し間延びしている部分もありましたが、興味深い作品ではありました。
広がるアマゾンの大自然。口噛み酒チチャ、聖なる薬として語られるアヤワスカ、そして昔からの薬草たち。とはいえ現代と完全に隔離されているわけではなく、医療も政治も少しはつながっている。そのバランスと葛藤が、実に興味深く映る。『森を汚染するってことは結局自分を破壊することと同じなんだ』と語る人々の言葉に耳を傾けると、胸を打たれる。日々一生懸命生きる人たちの姿を見るだけで、熱い気持ちがこみ上げてくる。
ローサやマイキュア、アヤワスカ、アマゾンの薬草は、科学者以上に価値ある存在だ。善悪の判断は、その人の文化的背景や生まれ育った環境、世界をどう見るかという視点次第で、簡単に反転してしまう。
アマゾンで生活する男は強さが求められる!
近代医療よりも、祖先から受け継いだ薬草の力を活かしている。
森とアマゾンに寄り添いながら生きる。
私には到底できない生き方だ。
この監督があの方たちとしっかり溶け込んで撮影している様子を見て、心が温まった。